詩 都市 批評 電脳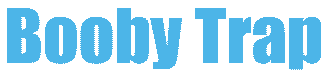 第10号 1993.10.20 206円 (本体200円)〒154 東京都世田谷区弦巻4-6-18(TEL:03-3428-4134:FAX 03-5450-1846) 編集・発行 清水鱗造 5号分予約1000円 (切手の場合72円×14枚) |
詩 都市 批評 電脳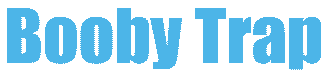 第10号 1993.10.20 206円 (本体200円)〒154 東京都世田谷区弦巻4-6-18(TEL:03-3428-4134:FAX 03-5450-1846) 編集・発行 清水鱗造 5号分予約1000円 (切手の場合72円×14枚) |
| 木の前の写真 |
布村浩一 |
|
| みどりご |
倉田良成 |
|
| [組詩] 路地から路地へ |
清水鱗造 |
|
| バタイユ・ノート2 バタイユはニーチェをどう読んだか 連載第3回 |
吉田裕 |
3 共同体論の視野 前回のノートで、次には個人名に限定されない思想上の問題を一般的に扱いたいと書いた。そうした思想的な問題は、指導者原理の問題、軍事性の問題、反ユダヤ主義の問題等多くあるが、それらの中で共同性という問題を取り上げるならば、これら数多くの問題を、かなり包括的にとらえることが出来ると考えられる。 共同体をどのように考えるかは、ファシスムにとってもバタイユにとっても、ということは、確認しておかなければならないが、両者にとってだけというのではなく、20世紀の思想のあらゆる流派にとって最大の問題の一つであった。バタイユは、〈古典的モラルの拒絶は、マルクシスム、ニーチェイスム、民族社会主義に共通している〉といっている(「ニーチェと民族社会主義」 6-187)。この言い方から、いくつかの思想的な運動体には、近代に対する批判を共通させ、そのうえで差異をもっていることがわかるだろう。共同体の問題も、同じ筋道の上であらわれる。 近代資本主義は、農村人口を労働者として引き寄せることで発展してきたが、それによって農村が持っていた共同体としての性格を、人々から奪い取った。しかしその見返りとして、新しい共同性を与えるということはなかった。都市の生活の中で、人々は単なる個人として、ふるまうことを促された。この変化は一方で、近代的自我の確立という美名を与えられたが、同時に人間の一方の本質としての、少なくともそれまで保持していた本質であるところの共同性を失うことであって、それは近代の人間に、他者から切り放されたという孤独感と喪失感を与えたのである。この喪失感は、第一次大戦によって、あらゆる階層と地方の出身者が無差別な個として扱われるという経験を経ることによって、不安にまで強められることになる。するとこの不安は、失われた共同体を、あるいは新しい共同体を求めるという希求となって現れることになる。たとえば学問の上では、このころ社会学や文化人類学といった新しい領域が現れるが、その出現の理由の一つに共同体への関心の高まりをいうことができる。 マルクシスムとファシスムについて簡単にいうならば、前者は共同体を階級というかたちで、後者は民族あるいは国家というかたちで実現しようとしたといえるだろう。 バタイユの関心の広がりも、この大きな暗黙の関心に導かれている。たとえば彼には最初から強い宗教への傾斜があったが、宗教といってもそれは、ただ神の存在を問うというのではなく、また神と個人の関係というのでもなく、宗教の意識は供犠の実践によって成立する共同的なものだという認識によっていた。また20年代に現れるフロイトへの関心も、同時代のシュルレアリストたちのフロイトが無意識とリビドーの理論家であるのに限られていたのに比べ、バタイユの場合は、それに加えて「トーテムとタブー」等の集団心理学のフロイトであった。彼は33年に「社会批評」に「ファシスムの心理構造」を書いているが、これは当時の左翼の間で定式化されつつあったファシスム理解、つまり、〈権力を握ったファシスムは、……金融資本のもっとも反動的で帝国主義的な部分の公然たるテロリスム的独裁である〉という35年のディミトロフ・テーゼに定式化されることになるような経済至上主義的な理解とは、異質なものであって、ファシスムを集団形成の新たな方法を案出した運動体としてとらえるものであった。そこにバタイユの共同体への関心の強さをみることが出来る。また彼は37年には、実質的な活動はほとんどなかったものの、ボレル博士やレーリスとともに「集団心理学会」なるものを設立している。これは「アセファル」や「社会学研究会」と同じ時期のことである。 他方ファシスムの側にも、共同体への志向は色濃く現れている。そもそもファシスムという言葉のもとになったイタリア語のファッショと言う言葉は、「束ねる」という意味を持っていて、この運動は人間の共同性を作り出すことを目的として開始されたのである。この運動は第一次大戦に従軍した元兵士たちの交遊から生まれたが、それは戦場での死を賭した体験の中ではぐくまれた友愛を基礎としていた。帰還兵士の集団を発端に持つというこの始まり方は、ドイツ・ファシスムの場合でも変わらない。初期のナチスム運動の中心となったのは、擬似的な軍事組織であった突撃隊(SA)の活動であったからだ。この求心力の強い集団は、ついで、資本主義の発達によってプロレタリア階級と資本家階級に両極化しつつあった社会の中で、後者に上昇することは出来なかったが、前者に落ちていくことも心情的には肯定できなかった浮遊する中間層を引きつけつつ、いっそう拡大されることになった。 これに対して、いわゆるデモクラシーの側からは、共同体という問題は、それほど大きくはあらわれてこない。なぜなら、デモクラシーとは、人間を共同性から解放された個体をしてとらえるところに成立するものであったからだ。だから共同体論は、少なくともある程度まで、デモクラシー批判の色彩を持つことになる。 共同体をどのように考えるかという問題は、まずなにを基盤にして共同体を構成しようとするかという点から考えることが出来るだろう。だがこの点からすでにドイツ・ファシスムとバタイユの間には、はっきりとした差異が現れる。後者にとって共同体の基礎となったのは、民族社会主義という名が如実に示しているように、民族であった。ドイツ・ファシスムの標語の一つに「血と土」というのがあったが、ファシスムは一つの土地に定住した民族というものを、共通性として取り上げ、共同性を再構成しようとした。ローゼンベルクに触れて、バタイユは次のようにいっている。〈反キリスト教主義が求められ、生が神化される時、彼らの唯一の信仰とは人種なのだ〉と。この人種的民族的な統一性を高めるものとしての神話や伝説が強調される。そして祖国の観念と愛国主義が称揚される。この称揚は、必然的に視線を過去の方に振り向けることになる。だがバタイユが、激しくニーチェを対立させるものの一つは、この過去への志向に対してである。ニーチェのワグナー批判は、ゲルマン神話への過剰なのめり込みに対する批判である。またニーチェは自分のことを、過去に属するものではなく、〈未来の子ども〉であると言っているからだ。ニーチェにとって未来とは、過去からくる規定を拒否する根拠だったのである。この対立の示唆は、「ニーチェとファシストたち」にも「ニーチェと民族社会主義」にも現れる。ここでは後者から引用する。〈ニーチェは奇妙にも自分のことを「未来の子ども」であると言っていた。彼はこの名前に、祖国を持たない自分の存在を結びつけていた。実際のところ、祖国というのは、私たちのなかで、過去に属する部分であって、ヒトラー主義はただこの部分に依拠してのみ、その価値のシステムを打ち立てたのであり、それは新しいなにものをももたらさないのである〉。 復古主義的な共同体思想は、近代に対する反動として、ロマン主義的な色彩を帯びてしばしば現れたものだが、ファシスムにおける特徴はその著しい急進性であった。それによってこの種の共同性の特性ははっきりとあらわれる。それは二つの局面であらわれている。一つは外側に対して発揮されるもので、共同性を保持するために、この共同性を共有しないもの、すなわち異端を徹底して排除しようとする傾向が強く現れることである。いうまでもなくこれは反ユダヤ主義である。もう一つは内側に向かうもので、共同性を保持する具体的な人物を求め、それに従おうとする傾向を生むことになる。これは指導者原理の発端であり、また他者への服従という軍事性の始まりである。 バタイユはこの二つの帰結に対して、ニーチェの思想が真っ向から対立するものであることを証明しようとする。まず反ユダヤ主義に対してだが、彼は〈ヒトラー主義にとって、ユダヤ人憎悪ほど本質的なものはない〉(「ニーチェと民族社会主義」)と述べて、反ユダヤ主義が、単なる現象ではなく、ファシスムの本質に属するものであることを明らかにした上で、すでに前回引用したような、〈人種などという恥知らずの悪ふざけにはまりこんでいるような者どもを決して訪問するな〉というニーチェの断言を数度にわたって引用するのである。 他方指導者原理に対する批判は、軍事性に対する批判と一体になっていて、後者の視点から見る方がわかりやすいだろう。ファシスムが帰還兵士の組織として始まり、ナチスにおいては、レーム粛清の直前には50万人に達し、国防軍を脅かすほどの巨大な組織に達していたということは、ファシスムに軍事的な性格が最初から備わっていたことを明らかにするに十分である。バタイユはドイツ・ファシスムの性格を、革新的に見えるところがあるとしても、その本質は反動的な軍事的愛国主義だと考え、〈もし民族社会主義の哲学というものがあるとすれば、それは自分たちと考えを同じくしないものを無視し、軍事的な強化に役立たないものを軽蔑する軍事的愛国主義である〉と言っている。 この軍事的な性格は、組織上では、上級者に対する絶対的な献身と服従の義務によって成り立っており、その最高部にあるのが、指導者としての総統に対する献身と服従である。しかし、この連鎖をもう少し子細にみていくと、より原理的な姿が見えてくるだろう。兵士が上官に献身し服従するとき、それはすなわち前者が後者のために存在しているということ、他者のために有用なものとして存在すると言うことにほかならない。 ところで他のものに対して有用であるという性格は、バタイユがもっとも激しく嫌悪したところの性格であった。そのことはすでに33年の記念碑的な「消費の概念」で疑問の余地なく明らかにされている。人間には生産のためではない消費、計算と合理性を越えた純然たる消費というものがあり、それを実践しうることが人間の動物に対する優位であり、また人間の中の高貴な人間と凡俗な人間を差異づける。そしてニーチェの思想は、ほかのなにごとかに応用されて有用であるといったところはいささかもなく、ただ思想としてのみ存在するような思想であった。それは政治的に利用されることを断固として拒否する思想であった。バタイユは「ニーチェとファシストたち」の中で、次のように言っている。〈ニーチェの原則は、利用されることはできない〉、あるいは〈反ユダヤ主義、またファシスムであれ、社会主義であれ、使用ということはあり得ない。ニーチェは、利用されるままになることを肯わない自由な精神に向かって語りかけるのだ〉と。 これら表裏一体になった反ユダヤ主義と指導者原理に対するバタイユの反応はどのようだったか。あまりに単純すぎる反証だとしても次のようなことは、あげておかねばなるまい。35年頃離別するが、彼の最初の妻シルヴィアはルーマニア系のユダヤ人であったし、彼にはエリック・ヴェイユをはじめ多くのユダヤ人の友人があった。また彼は36年に雑誌「アセファル」を発刊させ、また翌36年には同名の秘密グループを発足させるが、アセファルとは、頭脳を表す単語セファルに、否定の接頭辞がついた表現であって、それは雑誌の表紙のマソンのデッサンが明瞭に示しているように、無頭の怪物の意であった。この怪物は、頭脳すなわち理性の否定であると同時に、指導者を拒否する共同体の意味でもあったに違いない。そしてこの集団は、たしかに秘密結社の閉鎖的な外貌を持っていたが、バタイユのエロチックな地下出版物の言語と同じく、外側に向かって開く亀裂をそなえた共同体であったはずである。 |
| 塵中風雅 (七) |
倉田良成 |
貞享五年九月、『笈の小文』の旅を終え更科経由で江戸に帰った芭蕉は、伊賀上野の卓袋宛に書簡をしたためている。 卓袋。万治二(一六五九)年生まれ、宝永三(一七〇六)年没。享年四十八。伊賀上野の富裕な□糸商で俳人。伊賀蕉門のリーダー格であった服部土芳を通じて蕉門に入る。貝増(かいます)市兵衛。別号、如是庵・如是軒。屋号、□屋。蕉門の撰集に彼の作品が掲載されたのは『猿蓑』が初出。子息の蝶伽も蕉門であった。当書簡を含む貞享五年の三通の芭蕉書簡には卓袋とのこまやかな交情ぶりがうかがえる。 以下、全文を引く。 名護(古)屋迄之(までの)御状、□(ならびに)加兵へ(衞)持参、共に相達し候。先以姉者人御事(まずもつてあねじやひとおんこと)、兼而(かねて)急々に見請(うけ)候故、貴樣ヲ別而頼置申(べつしてたのみおきまうし)候處、愈御見届(いよいよおんみとどけ)、大慶に存(ぞんじ)候。一両年不自由不調之(の)事共、さてさて殘多(のこりおほく)いたはしく存候。加兵へ事も、内々何事ぞは出かし可申(まうすべく)と存候。此度(このたび)之事は小事に而候。先仕合(まづしあはせ)に御ざ候。不調法一ぺん事に御座候へば、くるしからざるあやまちと被存(ぞんぜられ)候。貴樣路金など御とらせ被成(なされ)候よし、半左衞門殿より具(つぶさ)に御申越(まうしこし)感心申候。扨(さて)は加兵へ事、寒空にむかひ、単物(ひとへもの)・かたびらばかりにて丸腰同然之躰、ふとん一牧(枚)用意なく候へば、當分何から建立可致(こんりふいたすべき)やら、草庵隱遁之客にあぐみものに而候へ共、拙者国に居申(をりまうす)時より不便(不憫)に存候ものに而候へば、今以(いまもつて)不便共とかく難申(まうしがたき)事共、誠(まことに)わりなき仕合に□(候カ)。先春まで手前に置(おき)、草庵のかゆなどたかせ、江戸の勝手も見せ可申(まうすべく)候。四十余の江戸かせぎ、おぼつかなく候。奉公とては、大かた相手有(ある)まじく候。寺かた・醫者衆の留主守などゝ云(いふ)やう成事(なること)か、何とぞ江戸の事に而御座候間、天道(てんたう)次第と存候。あまり能事(よきこと)も有まじきと、かねて御覚悟可被成(なさるべく)候。誠不埒(まことにふらち)に候はゞ、かねたゝキと拙者も存居申(ぞんじをりまうし)候。無是非(ぜひなく)候。便りもしかとせず候間、早々申殘し候。以上 九月十日 松尾桃青 □や市兵へ(衞)樣 御老母・御正(おまさ)殿・子共、御無事之よし、珍重(ちんちように)存候。梅軒老・權□□□(左衞門カ)、与兵え(衞)殿、預御状(ごじやうにあづかり)候。跡より御□(報カ)可申上(まうしあぐべく)候。 まず文面は困窮のうちに亡くなったとみられる「姉者人」について触れられている。すなわち「先以姉者人御事、兼而急々に見請候故、貴樣ヲ別而頼置申候處、愈御見届、大慶に存候。一両年不自由不調之事共、さてさて殘多いたはしく存候」というところであるがこの「姉者人」が誰であるのか見解の分かれるところであるらしい。芭蕉の縁者とも、卓袋の縁者とする説もある。だが、卓袋の縁者とするには「貴樣ヲ別而頼置申候處」といういいかたがかえって不自然であるし、だいいち裕福な商家であった卓袋に「一両年不自由不調之事共」という事実はなじまない。芭蕉の縁者であるとすればどうか。じつは芭蕉の実姉は早世している。ここに貞享年間と特定されている兄・半左衛門宛の芭蕉書簡の断片がある(今回テキストとして取り上げた書簡中の「半左衞門殿」は土芳服部半左衛門と推定されている)。 かれらが事までは拙者などとんぢやくいたすはづ(ず)に而も無御坐(ござなく)候へ共、一(ひとつ)はあねの御恩難有(ありがたく)、二(ふたつ)、大慈大悲の御心わすれがたく、いろいろ心を碎(くだき)候へ共、身不相應之事難調(ととのへがたく)候。其身四十年餘寝てくらしたる段、各々樣能御存知(おのおのさまよくごぞんじ)に而御坐候へば、兔も角も片付樣之(かたづくやうの)相談ならでは調不申(ととのひまうさず)、さてさて慮外計申上(ばかりまうしあげ)候。御免可忝(ごめんかたじけなかるべく)候。 ここでは「あね」とおそらくは亡母について、なんらかの合力を兄から申し込まれていたことに関しての断りを入れているのだと推測される。ありていにいえば、これは亡母の追善供養と「あね」すなわち「兄嫁」の医療費にかかる金子を頼まれたのだという説にしたがっておく。かねてから兄嫁の臨終が近いことがわかっていたという事情は、この書簡からも知られるのである。それにしても芭蕉のこの書きぶりから、それが少なからぬ額のものであったことは想像にかたくない。そしてその断り方がいかにも芭蕉らしい。つまり「其身四十年餘寝てくらしたる段」という部分だ。いわば「世間」的には無能者であるという姿勢が、付け付けられ、絶えず前進してやまない俳諧における練達の師の、強固な背景であったということは逆説でもなんでもない。「貧」は芭蕉にとってひとつの思想でありえた。むしろそれゆえにこそ、彼は貴人にも富商にも知己を持つことができたし、またいっぽうでは路通のような風狂乞食とも師弟の関係を結んだが、芭蕉自身が乞食の境遇にあったわけではない。そうであるなら半左衛門も金銭的な助力など頼むはずもない。芭蕉にもある程度の収入は予想していたものと思われる。「僧に似て塵有(ちりあり)。俗にゝて髪なし」と『野ざらし紀行』にあるように、彼は非僧非俗、筋金入りの俳諧師であっただけだ。 ほんものの乞食に近い境遇にあるのは書簡の次の部分に登場する人物である。 加兵へ事も内々何事ぞは出かし可申と存候。此度之事は小事に而候。先仕合に御ざ候。不調法一ぺん事に御座候へば、くるしからざるあやまちと被存候。貴樣路金など御とらせ被成候よし、半左衞門殿より具に御申越、感心申候。(中略)先春まで手前に置、草庵のかゆなどたかせ、江戸の勝手も見せ可申候。四十余の江戸かせぎ、おぼつかなく候。奉公とては、大かた相手有まじく候。寺かた・醫者衆の留主守などゝ云やう成事か、何とぞ江戸の事に而御座候間、天道次第と存候。あまり能事も有まじきと、かねて御覚悟可被成候。誠不埒に候はゞ、かねたゝキと拙者も存居候。無是非候。 まことに不憫ではあるがせんかたもない、といった芭蕉の表情が浮かんでくるような文面である。加兵衛なる人物はこの書簡以外にはまったく知られることのない人であるが、なにやら不祥事を犯して国元にはいられなくなったらしいことがわかる。それほどの重大事ではなさそうだが、「内々何事ぞは出かし可申候」といわれているように、初めから何か薄幸の影がまとわりついている男であったようだ。卓袋に関係のあった人間ででもあるのか、江戸までの路銀などをめぐんでもらっている。とにかく身ひとつで江戸の芭蕉を頼って出てきたわけである。しかし「四十余の江戸かせぎ、おぼつかなく候」と芭蕉に断じられているように、当時の常識では「老年」といえるほどの齢にさしかかった独り者の再就職は難しい。ふつうの奉公先は無理でも、寺男とか医者の留守番役ならまったく不可能ということでもあるまい。とにかく広い江戸のことだからなにごとも運しだいというところか。それもままならずいよいよ窮すれば鉦叩き(物乞いの一種)にでもなるしかない、と芭蕉は腹をくくっていたようである。ここらあたりの芭蕉のまなざしは充分に温かいが、湿ってはいない。それは『野ざらし紀行』の次の一節に共通するものがある気がする。 冨士川のほとりを行(ゆく)に、三つ計(ばかり)なる捨子の、哀氣(あはれげ)に泣有(なくあり)。この川の早瀬にかけてうき世の波をしのぐにたえ(へ)ず。露計の命待(まつ)まと、捨置(すておき)けむ、小萩がもとの秋の風、こよひやちるらん、あすやしほ(を)れんと、袂より食物(くひもの)なげてとを(ほ)るに、 猿を聞人(きくひと)捨子に秋の風いかに いかにぞや、汝ちゝに惡(にく)まれたる歟(か)、母にうとまれたるか。ちゝはなんじを惡むにあらじ、母は汝をうとむにあらじ。唯これ天にして、汝が性(さが)のつたなき(を)なけ。 古来問題とされてきた箇所であり、また芭蕉特有の文飾がないともいえないが、まずは言葉どおりに受け取っておいてよさそうである。冨士川のほとりで泣いていた幼子の像はそのまま加兵衛にかさねられる気がする。「貧」は絶対的なところまで来ると、あまりに人間的でありながら、一種メタフィジカルなイメージとなる。じつはここに、いままで人間が主体的には解決しえていない普遍的なテーマがあるのだが、たとえば親鸞ならばここで称名を唱えるところであろうか。芭蕉は同じところで一句を投げ出す。書簡では加兵衛に対し、「先春まで手前に置、草庵のかゆなどたかせ」とあるように、その保護を「春まで」と明確に限っている。おそらく『おくのほそ道』の計画などすでに立てていたのであろう。この態度も、捨て子に対するそれとよく似ているといえる。ここに私は芭蕉の冷酷さを見るよりも、表向きには妻子を持たず、生涯ある種の食客でありつづけた彼の、よく矯められた湿りけのない孤心を感じるのである。 ところで芭蕉自身は自らの「貧」をどう見ていたのか。そこにはいくつかの例証がないではない。まずこの時期の作として、 米買に雪の袋や投頭巾 というものがあるが、これは芭蕉ではなく路通による真蹟が残されている。路通はこのとき、深川芭蕉庵の隣庵に仮寓していた。このことは元禄元年十二月五日付の尚白宛芭蕉書簡であきらかである。書簡のなかで芭蕉は路通のことを「狂隱者」と評しているが、芭蕉庵には杉風のような幕府・諸侯の御用商を務める大パトロンも来れば、かくのごとき存在もしげしげと訪れている点に留意したい。ちなみに『けふの昔』に収められたこの句のバリアントの前書には「深川八貧」とある。いわゆる「近江八景」などの「八景」にことよせたものであろう。句意は、その日の晩餉の分だけのための米を買いに雪の夜の町へ出てゆき、投頭巾が雪にまみれてしまった、雪の白と米の白とのダブルイメージもそこにはある、と一応解いておく。句眼は投頭巾の「投」の一字だと思う。投頭巾はふつう踊り手や傀儡師、飴売り、小児などが用いるものとされる。上方では侠客などがかぶるという。そこにも風狂者の系譜を見て取ることができるであろう。 さて、元禄二年閏正月乃至二月初旬筆の猿雖(推定)宛書簡のなかでは、『ほそ道』の旅に出立するにあたっての覚悟が述べられている。 ……一鉢境界(いつぱつのきやうがい)、乞食(こつじき)の身こそたう(ふ)とけれとうたひに侘し貴僧の跡もなつかしく、猶ことしのたびはやつしやつしてこも(菰)かぶるべき心がけにて御坐候。其上能(そのうえよき)道づれ、堅固の修業、道の風雅の乞食尋出(たづねいだし)、隣庵に朝夕(てうせき)かたり候而、此僧にさそはれ、ことしもわらぢにてとしをくらし可申(まうすべく)と、うれしくたのもしく、あたゝかになるを待侘(まちわび)て居申(をりまうし)候。 「道の風雅の乞食」とは路通のこと。実際には『ほそ道』の旅に同行を許されず、随行したのは曽良であったが、旅の終わりに路通は敦賀で芭蕉らを出迎えている。「米買」が草庵の「貧」であるとすれば、旅における「貧」とは「やつしやつしてこもかぶる心がけ」、つまり乞食の境涯への希求だといえるだろう。ここには『発心集』や『撰集抄』などに登場する、中世をさまよったさまざまな聖たちの幻影が行き交っている。いいかえれば、泰平の「世間」のなかにあって、それとは逆の志向、あくまでも負をめざす欲求を芭蕉は欝勃として抱いていたようである。それが延宝・天和期のような中国というモダニズムではなく、日本の中世であったというところが、この貞享・元禄期における芭蕉の新しさであった。ただ気づいておいていいのは、その自覚にしても行動にしても彼は一個の「狂隱」にほかならないが、そこにはしたたかな俳諧師としての戦略があるということだ。菰をかぶることは同時に「やつされたもの」であるという点が、性狷介、本格的な逸脱者の路通とは決定的な違いを見せている。 それを示すのが『ほそ道』の旅の直後に書かれた、次の卓袋(推定)宛書簡(元禄二年九月十日付)のなかの記事である。 去年京屋方より被申越(まうしこされ)候、旦那御下屋布(敷)に御置可被成(おきなさるべき)よし、内證有之(これあり)候へ共、他客見舞も存知之外(そんじのほかの)衆も有之、又各々出入(おのおのでいり)も遠慮有之候間、わきわきにて小借屋(こしやくや)有之候はゞ、御かり樣之御心當(こころあて)可被成候。なる程侘たる分はくるしからず候。(中略)借屋有之候はゞ、筵にうすべり・へつゐ(ひ)壹(ひと)つ・茶碗十計(とをばかり)に而よく候間、随分御情(精)御出(いだ)し可被成候。 「旦那」とは藤堂新七郎家の当主・良長のこと。芭蕉には主筋に当たる。要するに芭蕉に藤堂家の下屋敷に住んだらどうか、という話が内々にあったということである。伊賀上野における芭蕉の評価をうかがわせるものであろう。たとえそこに「風雅」という形容がつくにしろ、ただの「乞食」のよくするところではない。結局下屋敷の一件は断っているのだが、表向きの理由としては、どんな連中がやってくるかわからないからというところがおもしろい。たぶん路通あたりのことが念頭にはあったか。下屋敷の窮屈な環境も予想していたことだろう。ただし芭蕉が郷里で一時を過ごす借家探しをしていたことは事実のようで、「侘たる分はくるしからず候」と、その斡旋を依頼している。そしてその「調度」といえば「筵にうすべり・へつゐ壹つ、茶碗十」ばかりでよいとする。ここには芭蕉自身の謙遜もあるにはあるだろうが、私はむしろ彼の風狂人としての自覚と自負を見ることができるような気がする。この「貧」のゆきつくところは、まるで高等数学のような手順により、「ことば」だけで達成された、次のような侘の極致の世界であった。 秋のいろぬかみそつぼもなかりけり (この項了)
|
| 「棲家」について 4 |
築山登美夫 |
この「出自の不明な暗喩」(前号参照)をことごとく〈解読〉してしまった評者がいる。彼は詩集『難路行』で吉本が「不明な暗喩」とした、作品「ミューズに」のミューズに冠せられた「黒い」という喩は作者のミューズであった女性が黒一色だけを好んでいたからだとか、また作品「風」の「真珠貝の孤独」の喩は真珠貝のようなやわらかい肉をもった孤独な女性のことだとか、作品「室内楽」の「太陽の誘惑のしみ」はそのような肌をもった(中年の)女性の喩だ、というように〈解読〉したのだ。 それも、これも、女性だと思います。そのような暗喩は、コトバの上で、昔から、ずっと知っていたことでしょうが、はからずも、現実の女性を通して、そのコトバの実在がよみがえってきたのです。詩をつくっていくインデックスの方向に、その暗喩がぴったりだったのでしょう。 女性、女性と、わたくしは言っておりますが、詩集『難路行』は、複数の女性に対するそれぞれの手切れの詩作品群のような気がしてなりません。(そうでない作品もありますが、それらは、あまりおもしろくない)そして、その手切れが、あぶなく自身にも及んでいる危険性を感じるのです。つまり、死の予感です。その手切れが「死」を招いていると言うのは、言いすぎでしょうか。 (長谷川龍生「末期の意識のなかに『愛』」――「現代詩手帖」88年10月号) あらかじめ云っておかなければならないのは、このように詩を作者の現実、私生活に直接にむすびつけようとする読解は、従来の詩批評が避けていたものだということだろう。それは作品が高度の虚構性をかくとくすることによって、現実をのりこえようとする作者のたたかいをうちけし、もとのもくあみにしてしまうとかんがえられたからである。またそのような読解をゆるすのは作品の虚構性の低さだとみなされたのである。だがそのような事情は、作者がはっきりとこの現実、この私生活に着地した場処から出発しているとかんがえることのできる直観の通路がふさがれようとするようなとき、そのことが作者の表出のたたかいにとって障害となっていると感じられるようなときには、再考されなければならない。そうするにあたって、この長谷川龍生のような理解のしかたはとても貴重なものなのだ。 だが長谷川の理解は、わたしからみて、自身にひきつけすぎた偏差の大きいもののように思える。たとえば鮎川の「黒いミューズ」を着衣の黒色とするのはあまりにも私詩的な読みにすぎるようであり、だいいち「きみの花柄のパンティを脱がせるためだったら/……詩なんかいつだってすてられるさ」という終連の「花柄」というのがつじつまが合わなかろう。この「黒いミューズ」の出自をたずねるなら、ボードレールを青年時代から晩年にいたるまで悩ませつづけた「黒いミューズ」、ジャンヌ・デュヴァルを連想するのがごく自然なのではあるまいか。 奇態な女神よ、夜のように色浅黒く、 麝香とハバナのいりまじった香りも高く、 どこかの魔術師、草原のファウスト博士が生み出した、 黒檀の脇腹をもつ魔女、真暗な真夜中の子よ、 (中略) おまえの魂の通気孔、その黒い二つの大きな目から、 おお無慈悲な悪霊よ! そんなに焔をそそいでくれるな。 地獄の河ではあるまいし 九回もおまえを抱けはしない、 (ボードレール「SED NON SATIATA (まだ飽きもせず)」安藤元雄訳) 黒いミューズは猛り狂って叫ぶ 嘘つき! 詩人の資格なし! ぼくらは闇の物象の 奇妙な ぞめき笑いの中に立ちつくす そこにいるのか いないのか? 沈黙は共通の敵だから ぼくは喋べらなければならない ……共通の穴である深い井戸にむかって (鮎川信夫「ミューズに」) 照応はすでに瞭然としているが、じっさいに鮎川の「ミューズ」がボードレールの黒白混血の愛人ジャンヌのように浅黒い肌をもっていたかどうかは重要ではない。それよりも、 『難路行』の他の詩句から引けば、狂う寸前の眼つきをしてじぶんの好きなものを数えあげ、さいごに「あなたなんか大きらい!」と叫んだり(「幸福論」)、舌足らずの棘にみちた手紙で男を非難してみたりする(「青い手紙」)、わがままでヒステリックな過敏さと無神経さをあわせもち、同時に男を魅惑してやまない感覚性と官能性をそなえた、つまりは男を悩ませるために生まれてきたような女との断ち切れない関係(「おお無慈悲な悪霊よ!」)そのことが、「ミューズ」に冠せられた「黒い」という喩の意味なのだ。 長谷川は『難路行』を複数の女性との手切れの作品群だというが、わたしにはむしろ「手切れ」の不可能性をこそモチフとしているように思えてくる。この不可能性こそが、死の触感に鮎川を近づけ、おののかせたのだ、と。 |
| Booby Trap 通信 No. 1 |