詩と批評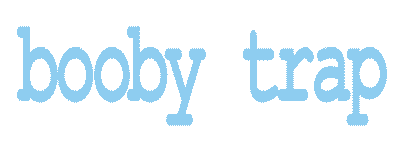 第2号 1986.11.24 500円〒154 東京都世田谷区弦巻4-6-18(TEL:03-3428-4134) 編集・発行 清水鱗造 3号分予約1500円 |
詩と批評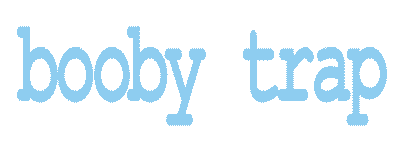 第2号 1986.11.24 500円〒154 東京都世田谷区弦巻4-6-18(TEL:03-3428-4134) 編集・発行 清水鱗造 3号分予約1500円 |
| 空をとんだ弟子 |
福間健二 |
ほんの七、八ヶ月前のことだ。ぼくはまだ山の中にいて、修行をつづけていた。もう先生も仲間の弟子たちもいなくなっていたから、修行といってもかなりいいかげんなものだった。さぼろうと思えばいくらでもさぼれるんだから。まあ、できるだけ食べないようにして、木の下か小屋の中にすわって、ときどきおかしな声でうなっていた。食べる量を極端にへらしてしまうと、あまり眠らなくてもいいようになる。とにかく時間がたっぷりあって、ひとりになって最初のうちは、その時間をだれにも邪魔されずに使えると思うとそれだけでうれしくて、もうそれだけで愉快になって笑い転げていたりしたが、だんだん悲しくなってきた。すわっていられなくて、山の中を歩きまわり、くたくたになってまだ体がひとりでにばたばた動きだし、目からは涙があふれだし、マントラを唱える声は泣き声になってしまった。ふいに先生のことがなつかしくなった。先生というのは、もちろん、きみがいつか「かっこうはキリストみたいだけど、なによ、いつもヘラヘラしているだけじゃない?」といったあの人のことだ。結局、あの人に十年以上もつきあって、いまこんなに自分がつらいときにそばにいてもらえないわけだと思った。先生も変わった。だんだんむずかしい顔をするようになっていって、そしてまったくあっけなく山をおりてしまった。ぼくはどうにもやりきれなくなって、小屋のちかくの頂のひとつに駆けあがった。自分が許せるつもりでいたことが許せなくなっている。それをあさましいと思った。黒い空が目の前にあった。その下に黒い森、さらにその下に黒い谷間があった。ここでなにか起きねばならぬ。このままでは、いままでやってきたことが全部むだになる。そう思った。山は黙っていた。風のない、しずかな夜だったのだ。しずかにじっと動かずにいる森を見下ろしているうちに、自分もこの何日かじたばたし、泣きわめいていたのが信じられないほどしずかになっているのに気づいた。いつのまにか足がすべって、頂のふちのところにいた。そして、いまだと思うと、ふっと足がうきあがって、ぼくは空にとびだしていた。一瞬、死ぬ気だったのかと思ったが、そんなことはなかった。ゆっくりと森へ、さらに谷へと舞いおりていった。ああ、人間ってこうなんだなと思った。それができないと困るというところのぎりぎりまで行けば、なんだってできるんだ。できることしかできないというのは、そのとおりだが、できるというのは、そうしないとどうしようもないところまで追いつめられているときに自然にやってくる力にしたがってできるようになるのであって、無理に努力してできるようになるんじゃない。むりしてやっても、できたことにはならない。できるという、ちゃんとした必然のあるところまで行けば簡単なのだ。できなきゃならない、そうならなきゃならない状態にはいって、あとはすーっとラクに手ばなしで、ということは自分の力なんかはまったく使わずにやってしまうのが、できるということなんだ。これは、そっくり先生が昔いっていたことだ。このとき、空をとんで、ぼくはそれがよくわかった。宙に浮きながら、すぐよこで先生がへらへら笑っていると感じられ、うれしかった。空をとんだというよりも、山から森の木々の上をかすめるようにして谷へ舞いおりたというのがほんとうだけれども、おりるのが案外むずかしかった。谷底の岩のなるべくたいらそうなのにおりようとしたんだ。ところが何度やっても、足がついた瞬間にはずみがついてはねかえり、またフワッと浮きあがってしまう。しかたがないから空中で姿勢をひっくりかえして、顔と肩のへんで着地した。そして気絶してしまった。 気がつくと明るくなっていた。小屋へあがっていく途中、一枚の紙きれを拾った。すっかり忘れていたけれど、それはぼくがひとりになってすぐにふざけ半分で森の中にばらまいたビラのひとつだった。「この世のややこしさに疲れた人、いっしょに修行しませんか?」とぼくは書いていた。拾ったビラには「あいかわらず馬鹿をやってるんだな ナカマル」と書きこみがしてあった。ぼくはびっくりした。ナカマルというのは、ぼくの古い友だちの名前だ。そのナカマルはたしかアメリカに行っているはずだった。もう十年以上会っていないから、その後どうなっているかわからないが、最後に会ったとき、かれはこれからアメリカに行ってビジネス・スクールとかいうところにはいり、そこを卒業したら事業の経営者になるといって、片道の航空券をぼくにみせた。「もう日本には帰ってこない。日本はおれにはあわないんだ」とも「ちゃんと綿密に計画をたてているから、大丈夫。野垂れ死にしたりはしないさ」ともいった。そのナカマルがこの山まできてぼくのビラを読んだのだろうか。あいかわらず馬鹿をやっている。それはどっちこのとなんだ。ぼくはまた涙ぐんでしまった。山からおりて、ナカマルのことを知っているかもしれない連中に何人か電話してみた。だれもかれの行方を知らなかった。ぼくがビラの書きこみのことをいうと、「おまえが自分で書いたんじゃないか」とせせら笑ったやつもいる。しかし、それはぼくの字ではなく、なつかしいナカマルの字だった。山に戻り、あの頂に立ってみた。ぼくはそこを「ネバナラヌの岬」と名づけた。山で岬というのはおかしいかもしれないが、それがぴったりくる気がした。しかし、もう一度とんでみようとは思わなかった。二度目はむずかしいのだ。たぶんとべることはとべるだろうが、心も体もそれを必要としていないのにやってしまうところから堕落がはじまる。いいかげんにやっているうちにきっと失敗する。そこでまたひとつ勉強できるということになるのだろうが、とにかく一回やったというよろこびをネバナラヌの岬という名前といっしょにとりあえず大事にしまっておきたかった。まあ、もったいない気がしていたんだ。もうなんの目標もなくなっていたし、寒くもなってきていた。なにしろ、北だからね。ナカマルのことも気になったし、先生たちの残していったわずかな金をもって山をおり、ナカマルのような男(といっても、いまどんな漢字になっているか見当もつかなかったが)を見かけなかったかと人にたずねながら、まっすぐ南へ下った。台風が去ったある夜、ぼくは満月と海と恋人たちを見た。恋人たちはくそまじめに仕事でもするようにカチカチになって抱きあっていた。力の抜き方、それを教えてやれるのに、とぼくは思った。しかし、なんの関係もない二人であり、いくらかわいそうだと思っても、そもそもぼくが二人のやることを覗き見していることがいけないことだった。あと、その九月にやったことといえば、すばらしい顔をした年寄りの漁師の昔話をきき、おいしい魚をたっぷりと食べたことぐらいだ。魚は(ジャコやホシコ以外のということだが)まる半年ぶりだった。恋をする気分になれず、その恋人たちや漁師のいた海辺のさびしい町に二週間ほどいたのだ。そして十月には、その町から電車で一時間ほどの都会で、あろうことか、ぼくはフランス語を教えていた。 ぼくはフランス語なんてぜんぜんできない。でも大学の仏文科を出たと嘘をいったら、あっさりと採用されてしまった。昼間、その日に教えるところを必死で勉強して、それをもうずっと前から知っていたような顔をして、テキストに書きこみなんかもしないで、なんというか、まったくのはったり演技でおしえていた。夜の授業だけだったから、余裕があったのと、まだ記憶術の力が衰えていなかったから、なんとかもったといえるが、それにしても、冷や汗のかきっぱなしであった。ぼくがフランス語を教えるなんてとんでもない話なのだ。だって、授業の最初の日の朝にはまだエートルの現在形の活用も知らなかったんだから。まぁ、一時期、スペイン語をかじったのが、すこしは役に立ったかもしれない。先生の先生という人がメキシコ・インディアンだったから、メキシコに行ってその人から直接、術を授けてもらおうと考えたことあって、それでスペイン語をやりだしたんだけれど、そのうちに先生が方向転換して、メキシコはあまり関係ないというようなことになってしまった。だからスペイン語だってすっかり忘れていた。もしかしたら、ぼくはいまごろメキシコで本格的に野生人の暮らしをしていたんだなんて、フランス語を教えている文化的な雰囲気のなかでふと思った。そこは、もうわかったかもしれないけれど、カルチャー・ナントカというところで、となりの教室では活け花とかエアロビクスとかをやっていた。フランス語を習いにきている連中も、おばさんが多く、意外におとなしいというか、こっちがぼろを出さないようにかなりきびしい感じでおさえこむ態度をとっていたせいもあるかもしれないが、しずかな授業で、質問もあまり出ない。なにをいっても、素直にうなずいている。ぼくはそこにつけこんで、どんどんテキストを進んだ。ただ、中にひとり、亭主が警官だとかいう女がいて、ちょっとうるさかった。いわゆる好きそうな顔というのか、 いやらしい感じなのだ。退屈そうによそ見をしていたかと思うと、じっとこっちをみつめていて、ふと思いだしたように質問をする。授業の終わったあとも話しかけてくるのを、どうも上手にかわすことができなかった。 「肩がこるなんて、フランス語でどういうの?」 と甘えたようにいって、いかにも肩がこってしかたがないというしぐさをしている。こっちはふとどきっとして英語でたしかスティッフ・ネックだから(これは昔、弟子仲間のひとりにアメリカ人の牧師の子がいて、先生からはり治療を習っているときにそんな言い方をしていたのをおぼえていた)、と考えて、自信はなかったけれど、エーイ、まあいいやという気持ちで、 「クー・ドゥール。私は肩がこっているは、ジェー・ル・クー・ドゥール」 と応えた。そういった瞬間に、女が胸にかかえていた黄色い表紙の辞書の中のページが透視できて、ページの一枚一枚がものすごい速度でめくられ、あるページでとまった。そこに torticolis という見出し語があって、それだけが鮮明にみえた。とっさのことで、すらっとは読めない。もちろん、どういう意味の単語なのか、日本語の説明はぼんやりして読めないので、わからない。 「トーティコリ、そうもいうんだったかな」 といってみるが、「コリ」 なんてはいっているところも冗談っぽく、かえってどぎまぎしてしまい、それをごまかすために、 「肩こり、ひどいんですか?」 「まいっているの。ほら、こんなにパンパンだもの」 と片方の肩をぼくにちかづけ、さわってみさせようとする。 「ぼく、こういうのをなおす方面、ちょっと知識があるんだけど」 「指圧?」 「いや、もっとすごいやつ」 で、彼女を借りていた部屋に連れてきて、その「すごいやつ」をやってあげたわけだ。もちろん、そのあと、どんどんまずいことになっていった。冬が本格的になるころには、ぼくはこの女とその警官の夫から逃げるためにその市からだいぶ奥にはいった温泉町の旅館に仕事をみつけたが、女はそこにもきて、おどろくべきことをいった。ちょっと色気があるとかいっても、どうしてそんな女のために新聞の三面記事に載るようなことをしなくてはならないだろう。話だけだとしても怖くなって、今度は遠くまで逃げることにした。妹やきみのいる東京を素通りして大阪まで行った。 大阪に着いたときは、すっからかんになっていた。大阪には、前に一年半ほどいたことがあるから、知りあいが何人かいるつもりだったが、会えたのは小説家のMさんだけだった。Mさんは昔、「六白金星」という織田作之助の小説の題からとった名前の飲み屋をやっていて、そこに通ううちにぼくはかわいがってもらうようになった。Mさんも六白金星、ぼくも六白金星で、ひとまわり年がちがった。ほかにたよれるところもないので、図々しくMさんのところにいそうろうしていたのだが、奥さんが冬なのに半袖を着て、二五〇CCのバイクを乗りまわすような、たくましい人で、その鈍感さにぼくはあっ気にとられ、敏感に風邪をひいてしまった。この奥さんはいつもジーパンとTシャツで、かっこいいとかわるいとかいう次元を超越していたが、彼女のところにいまどきこんな田舎くさい服装があるのかといったかっこうの娘たちが集まって、わけのわからない勉強会をやっていた。奥さんが強気の大阪弁で人生哲学をまくしたてる。それをきいている娘たちのひとりが急にワッと泣きだす。そうなるとみんながワーワーやりあって、最後は奥さんもふくめた全員がないている。なんなのだろう。ぼくは機会をうかがってMさんにきいてみた。Mさんは奥さんには逆らわない主義らしく、 「なんや知らんけど、新手の金儲け考えてはるとちがいまっか。なんせ、ぼくの原稿料だけじゃやってけまへんからな」 と笑いながらいった。あるとき、ぼくはMさんのマンションの屋上で陽なたぼっこをしながら、坂道をこちらにむかってくるその娘たちを見ていた。わかりやすくいってしまえば、一昔前の民青といったダサイかっこうであるが、なにが悲しくてそんな、いまではよほど辺ぴな村の洋品店にでもいかなければ売ってないような服装をしているのだろうと思った。 Mさんの友人で印刷をやっている人がいて、その人の仕事を手伝うことになった。会った瞬間に、その人は病気だと思った。体中がむくんでいて黄色い顔をしていた。 「背中や腰やあちこちが痛うて痛うてかなわんのや。毎朝、ほんまに生きる気力があらへん」 と力なく年寄りじみた笑い方をしたが、きいてみるとぼくよりも年下だった。ぼくはこの人の体をなおそうと思った。手でさわったりする程度ではどうにもならない。お灸をすえ、漢方薬を飲んでもらった。似た病気の人間を知っていたから迷わなかった。ひとり暮らしで酒の飲みすぎ、おいしいものの食べすぎでそんな妙な体になったのだ。ぼくもかれの印刷所に住みこむことにして、動物抜き、砂糖抜きの野菜と穀物、豆類だけの食事をつくってあげることにした。ぼく自身、山をおりてからどんどん食事が乱れてきて、Mさんのところでは(ゼイタクをいっては叱れるが)だいぶインスタント・ラーメンを食べさせられたから、そういうまともな食事にきりかえたいと思っていたところだったのだ。考えてみるとこの印刷屋さんをむりやり病気にしたてて、自分に都合のよいように事を運んでいったようで恥ずかしいが、かれはべつに文句をいわなかった。それどころか、ブヨブヨと太って八十五、六キロもあった体がみるみるスマートになって、ぼくがきて一ヶ月半たったところで測ったら六十七キロという、その一七〇センチほどの身長の人としては標準体重にちかいところまで落ちたから、とてもよろこんで、「神さんがあんたをぼくにつかわしてくれたんやな」とまでいってくれた。だいたい研究熱心な人で、手や足は自分で灸をすえられるようになったし、ツボなども本でおぼえてぼくよりも詳しくなり、ぼくがそうまでしなくていいというのに、自分で知識を仕入れてきて圧力鍋で玄米を炊くことまではじめた。 給料は十万円の約束だったが、渡された封筒をあけてみると二十万円はいっていて、「感謝をこめて」と書いた便せんがそえられていた。ここでぼくはまた泣いてしまった。印刷の仕事のほうではドジばかり踏んで困らせ、治療のほうはただいい気になってなかばあてずっぽうでやっただけなのに、ありがたいことだ。感謝せんならんのはこっちや、と大阪弁が出た。給料をもらってすぐの日曜日に阪神競馬場に行った。関西の馬には知識がないというよりも、競馬をやるのがそもそもまる一年ぶりだったから、はじめはまったく調子が出ず、四レースやって二万ほどすったそのあと、もうやめて帰ろうかどうしようかと思いながら、パドックを人垣のうしろから覗きこんだら、小さくて黒い馬が薄いブルーの光につつまれていて、その馬が歩くところだけが奇妙にひやっとした空気が動いている。そんな気がした。競馬はやってきたほうだが、こんなことははじめての経験である。6番、ホワイトキング、もっていた競馬ブックの予想ではまったくの無印。黒い馬なのにホワイトとはと思って、ああ、馬主がきっと六白金星なんだと閃いた。そうだとしたら、6番にはいることになったとき、馬主は微笑みを浮かべたことだろう。このホワイトキングの単勝を一万円買った。人の少ない四コーナーの柵のところで見ていたが、6番は四コーナーはほとんどビリッケツできた。しかし、コーナーをまわったところで勢いがついたと思った。ゴールの様子ははっきりわからなかったが、かたまってはいった感じなので希望はたかまった。となりで見ていた男が「ホワイトキングや、大穴やんけ」といった。ぼくは体がふるえだした。単勝の配当は一二三〇〇円で、ぼくは一二三枚の一万円札を手にした。こんな金はどうせあっというまに消えてしまうと思って、なかから百万円を東京の妹におくった。それから記念にと思って、古本屋でみつけておいた織田作之助全集を買った。織田作之助が「競馬」という傑作を書いていたことも思い出していたのだ。 妹がぼくのお金を受け取ってどんな反応をしているか知りたくなったのは、やっぱりまだ修行が足りなかったということになるだろう。東京に電話を入れた。妹はおこっているみたいだった。「つかいたくないんだったら、預かっといてくれよ」とぼくはいった。妹は親戚の連中のことを話した。それから、きみのことを話した。 「いまは、ひとりみたいよ。まだあの図書館に勤めているらしいわ」 「詳しいんだな」 「きこえてくるのよ。共通の知人がいるから」 妹は、すこし前まではきみがひとりではなかったような口ぶりだった。妹と話しているうちにぼくは東京に戻ろうかという気になってしまった。三月だった。Mさんに電話すると、「えらい寄り道しよったな」とかれはいった。Mさんはどういう意味でいったのかわからないが、「寄り道」という言葉からぼくはすぐにきみのことを考えてしまった。織田作之助全集は読みきれなかった。印刷屋のかれにあげるというと、とてもよろこんでくれた。かれももともと文学青年で、詩集や同人誌を安い値段で刷ってあげたりしている人間だった。三月七日、新幹線で東京駅に着いた瞬間、もうすぐきみに会う、ほんとうにすぐだと感じた。初対面の妹の亭主が、 「義兄さんも、そろそろ身をおちつけていいころですよ」 と訳知り顔にいったときも、ぼくの気持ちは平静だった。 「食えない人間だからね、おれは」 「食えますよ」 「いや、あんたにはまだわからないと思うけど、食えてなくとも、どうだっていいと思ってるんだ」 「ほんとうですか。不安にならないんですか」 「そういうことでは不安にならないんだ」 「おもしろいですね」 「おもしろくはない。ただ気楽なだけだ」 こういう二人のやりとりを妹は心配そうに見ていた。ひさしぶりに会った妹の緊張のしかたは、ぼくに両親のことを思いださせるもので、ちょっとつらかったが、どんな場面でもそんな心配そうな顔をしなくても生きていられるようになるためにおれは山にはいったりしたんだよ、といいたかった。いってもまったく通じないだろうとも思った。妹たちはお金を返すといってきかなかったが、いままでなにもしてやれなかった、結婚祝いだと思ってくれ、といってなんとか受けとらせた。偶然競馬であてたお金だったが、これがなかったら妹のうちにきても肩身が狭かったのかと思うと、なんだかおかしかった。 東京へ来て妹のところに泊った次の日が土曜日で、さっそく中山競馬場に行った。その日はまったく儲からなかったが、そこでマルタに会って、かれのところにしばらく転がりこんでいいということになった。大阪へ行ったあたりからツキがまわってきたな、と思った。いや、あの警官の奥さんだってなかなかの女だったかもしれない。こっちにまだ余裕がなかっただけのことで、ツキはもうずっと前からはじまっている。マルタは「昔、ずいぶん借りがありますからね。自分のうちだと思って気楽にしてください」といってくれた。マルタは、ハンバーガー・ショップの店長とかいうものになっていて、 会社が借りてくれている3LDKのマンションにひとりでいるという、こっちからすれば願ってもない暮し方をしており、昔からの気のよさはあいかわらずであり、しかもかれが店長をしている店はきみの勤めている図書館とおなじ町にあったのだ。 ぼくの三七歳の誕生日の朝、マルタは「今日はお祝いをしますからね」といって、待ちあわせる飲み屋の場所と名前をぼくに教えた。 「おれの誕生日がよくわかったな」 「ずっとおぼえてたんです。いつかいっていたじゃないですか、昔の陸軍記念日だとか」 とマルタはいって、そのあとちょっとへんな笑い方をした。きみからきいていたわけだ、その誕生日のことは。約束の店に行ってきみの姿をみつけたとき、ぼくはそれほどおどろかなかった。白いブラウスにレンガ色のカーディガン、それを首のところまできちんとボタンをとめて。あのときのきみの姿をぼくは一生忘れないよ。おどろかなかった。酔ったときに「頼むよ、会いたいんだ」とマルタにいっていたのだから。こうならなきゃならないことになっていたのだから。 きみのアパートへ来てから、ぼくは怖いくらいにいろんなことがわかり、いろんなことがはっきりした。それも、日常のなにげない動作をしているときに瞬間的にぱっと感じとってしまうのだ。ナカマルはとっくに死んでいる。あのビラの書きこみはやっぱりぼくがかれの字をまねして書いたのだ。空をとぶ前の、悲しくてやりきれなかった時期に。ナカマルは死んでいるけれど、ときどきぼくのうしろに立って、「もうおれはなにもいわんからな」とかつぶやくのだ。ヘラヘラ先生もくる。まだ生きていて、なかなかうまく商売をしているらしい。先生がではなくて、 しっかりした弟子たちがやっているんだろうけど。それから、妹はきみのことがきらいだ。きみのことをずっと監視していたんだ。まあ、あの百万円をあげられてよかったよ。それから、こんなことも思いだした。ぼくはある夜、マルタの悪口をいいまくった。すくいようのないお人よしだと。でも、そのお人よしにすくわれたわけだ。ぼくもまったく調子のいい人間なのさ。十年前から姿を消して、七、八ヶ月前には空をとんで、この春はきみのつくったおいしいものを食べている。でも、ぼくもこれからだよ。いちおう苦労をして空をとべる人間にはなったけれど、もう空はとばないだろう。何をするか、この地面に足をおいてじっくり考えなきゃいけない。よろしく。 |
| 鮎川信夫追悼 |
「戦中手記」は何回か読み返した。最近までかかれていたコラムは初期から表われている、文明批評への志向が出ていてジャーナリズムの良識みたいなものを目指していたと思う。詩についてのまとまった論考はもう書かないだろうな、という感じが晩年にはあった。詩について受け継がれるものは、計り知れないだろう。僕は鮎川氏に二度お会いしたことがある。石原吉郎記念講演会と「毒草」でインタビューを載せるために訪ねていったとき。講演会では同時期に発売された花神社の全集(これは厳密には全集でなく著作集)の、月報とまるっきり同じことをしゃべった。なんとなくなぜほとんど変わらない内容をしゃべるのか、推察できる気がした。訪ねていったときには石油ストーブに火がつかないで、お母さんに聞いていたのが印象に残っている。それから国保にはいっていないという話をきいてびっくりした。エッセイなどを読むと詩人の生活形態がうっすらとわかる。結婚しようとしまいと、どんな生活をしていようとそんなことはどうでもいいが、書かれたものから鮎川のエロスを探るときどうしようもなく『厭世』などのエッセイ集が重要性を帯びてくる。それは別にして、詩人のライフスタイルとして、学ぶところは多々ある。とにかく心の内部で鮎川の死を受け止めようと思う。(鱗) 連載についての註 木嶋の賢治論は、連続して書かれているものの一環としてある。編集者に連絡してくだされば、他の論考のデータをお知らせできる。清水の連載は廃刊になった「夜行列車」(二回連載)から続ける。 次号予告 〈座談会〉鮎川信夫について 福間、木嶋、清水 〈詩〉藤林靖晃、田中勲、二川原一美ほか 〈歌仙〉倉田良成ほか 〈批評連載〉木嶋孝法、清水鱗造 |
| 秘めごと |
田口育子 |
|
| ゲルニカ |
藤林靖晃 |
午前一時。焼けた砂の上。熱い土砂を噛む。かすかな、ほんのかすかな月の光。徐ろに歩く。一瞬の闇。ふいに三人目の俺が殺される。深い穴の中に俺は居る。一億回目の死? 耳をそばだてる。音が無い。音? 波の音は。風の音は。闇だけが続く。一万時間。闇。ただひたすら闇。空と地が付着した。世紀の終焉。 午後七時。ギラツク陽。裸ノ躯ヲ焼ク。走ル。タダ走ル。走ル。走ル。飲ム。飲ム。食ベル。食ベル。叩笑ガヒビキワタル。コノ群衆ハ誰ナノカ。四人目ノ僕ガ今生レタ。君ハ何処ヘ行クノカ。ニューエイジヘ旅スルノサ。ソコデ何ヲスル? 激シイ怒リヲ笑イニ代エルノダ。君ニハワカルマイ。僕ハ楽シムノサ。エ? 楽シムンダヨ。何ヲ? 何ヲッテ。ツマリ。何カラ何マデモサ。何ガソンナニ楽シインダ? 一切合財ガダ。ソンナ莫迦ナ。有ルンダヨ。捜セバ、エ? フフフ。 午後一時。私は五人目の私を求めて野原をかけめぐる。汗の塊に変化する。傷だらけの四肢は止まることがない。何ごとかしきりに到来する不可思議な声。声だろうか? 呟やき。その呟やきの中に人の形がうっすらと見える。いやそれは人ではないかもしれない。あるいはこれは夢なのかもしれない。夢の中の夢。いつ終わるとも果てしのない光景。追う。ひたすらに追い続ける。む。何かが見えはじめた。ただまっしぐらに追う。追う。むむむ。 午後八時。都会ノ路上。カツテ同胞ダッタ人タチハミナ姿ヲ消シタ。コレガ君ノ宿業サ。エ? 苦シイカネ。フフフ。出ルモノハ笑イダ。未成ノ嗤イ。俺ニハコノ汚レタ路サエアレバイイ。ソウシテ俺ハココニ立ッテイル。立チツヅケルノダ。ヒトリデ? 何ノ為ニ。理由ハナイ。フフフ。理由ナンゾイラナインダヨ。俺ト言ウ君。君ノタメニ一杯ノ水デ祝杯ヲアゲヨウ。サア。早ク、早ク。俺ハ沸トウスル大気ノ中ニ立チツクス。 |
| ビーンズが出来るまで |
荒川みや子 |
私に植物の束をくれたオジイサンと私達にそら豆を買ってきてくれたオバアサンにはさまれて軒下でそら豆を剥いた。私はオジイサンとオバアサンのムスコの嫁さんで、ムスコと夫婦であるからそら豆を剥かなければならない。五月や六月の夕方家族のものたちが、そら豆をざるに入れ準備をしなければならない。雨の日でもチリを払って私はそうする。オジイサン、脇にすわるとあなたの骨のまわりは春でも冬の木立ちが触れ合う音。がする。ガラガラもうすぐ骨が記憶したものたちで、いっぱいになり家中豆の木のような骨の林が生えるだろう。私は死んではいない。でもオジイサンより先に死ぬかもしれない。川を渡って、木立ちの方へ進んだから果実がぽとんと落ちるように、人間だから皆死ぬと思う。私は死にたくない。生きたい。のでトイレへゆく。空からふってくるモノや地上になるモノを喰べる。バカと言おう。マヌケ。オバカのトンマ。なんでもかんでもき・こ・え・る・よ。 川を渡って私はグミの林やクヌギの木立ちを歩く。私達の家の中にいるオジイサンとオバアサン。古い柱と古いタタミの中でそら豆を喰べてしまったヒトへ、水を取りに入る。「さ行の音ね。私達が夜抱き合って寝るひびきとはちがう。」「風の音ね。日曜日私達はビガーに乗っている。」空より低く、何か草で出来たモノが私の中に居る。私はビーンズと呼ぼう。それから霞立つ木立ちの奥へ杭を打ちにゆく。 |
| 風の日には耳をおさえて |
堀亜夜子 |
|
| 宮沢賢治論 連載第二回 緩やかな転換 ――報告者の位相から自己表現の位相へ―― |
木嶋孝法 |
○『鹿踊りのはじまり』 たしかに、作品には、 《ざあざあ吹いてゐた風が、いま北上の山の方や、野原に行われてゐた鹿(しし)踊りの、ほんとうの精神を語りました。》 と書かれている。けれども、実際に鹿踊りを見聞したことのある人でない限り、《いま北上の山の方や、野原に行われてゐた鹿踊り》という表現を文字通り鵜呑みにしたりはしないであろう。それすら、作者の創作かもしれないからである。しかし、次のような文章に接すると、この作品が、まんざら作者の想像力によってのみ創り上げられたものなのではなく、作者にとっては、むしろあたりまえの前提に下づいて創られていることを改めて思い知らされる。その、あたりまえの前提が、わたしたちにはよく見えないのだ。 《その夜江刺市梁(やな)川地区で珍しい行事の現場に立ち合うことができた。土地の今野昭三氏の斡旋によるものだったが、梁川では「獅子躍」と表記している例の鹿躍りの免許授与の儀式が参観できたのである。》 口拍子の発声音も記録しているので、それも引用させてもらう。 《タクツク、タッタコ、タッタコ ザンツク、ザンツク、ザッツァコ ザン、コ、ザン タッタ、コ、タ それは太鼓の革を打つ音とふち叩く音とをあらわしている。》(以上、島尾敏雄氏の「奥六群の中の賢治」より引用、日本文学アルバム『宮沢賢治』所収) 《のはらのまん中の めっけもの すっこんすっこの 栃だんご 栃のだんごは 結構だが となりにぃからだ ふんながす 青じろ番兵は、気にかがる。》 こちらは、鹿野歌う歌で五行詩になっているが、二行目の《すっこんすっこの 栃だんご》というところなど、明らかに「鹿踊り」の太鼓を叩く音か、土地の青年の口誦に材を求めたことは、疑いようもない。となると、わたしたちはどのような事態に遭遇したことになるのか。鹿踊りのはじまりというのは、これから鹿踊りが始まるよ、という意味なのではなくして、当時、花巻近郊で行われていた鹿踊りが、どのようにして始まったか、という意味なのだ。つまり、起源譚なのである。 とはいえ、手法的には、『かしわばやしの夜』や、『月夜のでんしんばしら』等と何ら変わるところはない。柏の木や電信柱を人間に擬えることが、賢治的な幻想の世界への入口であるとすれば、『鹿踊りのはじまり』もまた、鹿の擬装をした人間の身振りや、太鼓の革や縁を叩く音を、鹿の動きや歌に擬えているにすぎない。 《鹿は大きな環(わ)をつくって、ぐるぐるぐるぐる廻ってゐましたが、よく見るとどの鹿も環のまんなかの方に気がとられてゐるやうでした。(中略)もちろん、その環のまんなかには、さっきの嘉十の栃の団子がひとかけ置いてあったのでしたが、鹿どもの気にかけてゐるのは決して団子ではなくて、そのとなりの草の上にくの字になって落ちてゐる、嘉十の白い手拭らしいのでした。》 擬装「鹿踊り」の方の踊りの光景を想像する。腰に下げた太鼓のリズムに合わせながら、右足に重心を移したり、また、左足に重心を戻したりする。大きな輪が、中心に向って萎んでいったり、また輪が広がったりする。あるいは、個々人が、思い思いに鹿の仕種を模倣する。秋の野原に展開するそんな光景――。 たしかに、この踊りが、どんな目的で、いつ頃、どんな人々によって始められたのだろうという疑惑がぼんやり起こってきたとしても何ら不思議ではない。そして、意識的にか、無意識のうちにか、その疑惑に賢治が応えようとししたとても。しかし、自分で創作しておきながら、なぜ《わたくしが疲れてそこ(苔の野原―註)に睡りますと、ざあざあ吹いてゐた風が、(中略)鹿踊りの、ほんたうの精神を語》ったとしなければならないのか、その点は疑問である。自分が作ったと思われたくない、と思っていたことは確かである。世の中には、作品を、その作者の個人的な才能の現れと考えて、羨望や驚異の目で見る人もいるわけで、そういうふうに個人に還元されたり、才能を誇示しているように見られないように、風を隠れ蓑に使ったのだ。おそらく、そこには、自己顕示欲を諌めようとする、仏教でいう無我の思想が、眼に見えない強制力として働いているのである。当然、白樺派の「天才賛美」にみられるような、西洋的個人主義への反発もあったはずだ。 さて作品へ戻ろう。 〈風〉は、鹿踊りの見聞者に嘉十を選んでいる。湯治に出かけた嘉十は、途中で食事に栃と栗のだんごをとる。この際に、手拭いを置き忘れ、それを取りに戻ったところで、鹿の姿を見るのである。 蟻が見たきのこ、蛙が見たとうもろこし同様、手拭いが、鹿たちの未知の、興味の対象になる。うまく考えたものである。擬装「鹿踊り」の動作が、輪の中心に置かれた異物にこわごわ近づいたり、探りを入れたり、慌てて逃げたりするように見えたのである。そこで賢治は、手拭いを囲んで鹿の輪を配列したのである。しかも、鹿が出現しても不自然ではないように、手拭いの脇に栃のだんごの食べ残しまで置いて。これで、いつ鹿踊りが始まってもおかしくないように舞台装置が整ったわけなのだ。 一頭の鹿が、手拭いを栃のだんごの傍から取り除いたところで、歌と踊りが始まる。野原の真ん中で見つけたものは、すっこんすっこの栃だんご。栃のだんごはいいのだけれど、となりに体を吹き流す、青、白、ぶちの見張り兵は気に懸る。青白番兵はふんにゃふにゃ。吠えもしなければ、泣きもしない。痩せて長くて、ぶちぶちで、どこが口なのか、頭なのか、日照り上りの大きななめくじかもしれない。一頭の鹿が歌う、こんな内容の歌に合わせて、他の鹿たちが踊り出す。一度は、嘉十も自分が人間であることも忘れて、この輪の中に飛び出そうとするが、思い留まる。しかし、二度めにはもう自分を制することができない。驚いた鹿たちは、当然踊るのを止めて逃げ出してしまう。秋の夕べの鹿踊りは終ったのである。 夏の夜の柏の踊り、月夜の電信柱の行進、秋の夕べの鹿踊り。いずれも、同一の手法を用いながら、『鹿踊りのはじまり』だけが、結果的に起源譚になってしまった。ここから、実在する奇妙な森の名前の由来を探る『狼森と笊森、盗森』への道行きと、〈はじまり〉という言葉が、オープニングとオリジンの二重の意味に取れるのと同様の、意味の二重性を逆手にとった『注文の多い料理店』への道行きが見える。 振り返れば、賢治の農夫への眼差しが微妙に変化してゆく様が窺える。 『葡萄水』では、作者は耕平に好感を持っていなかった。『かしはばやしの夜』においても、導入部では、同じような姿勢で入っていったのだと思う。ところが、「赤いしゃっぽのカンカラカンのカアン。」と清作が怒鳴ったところから、清作に対する態度が微妙に変化していく。それは、たとえば、絵描きの自嘲的な態度となって現れる。恭一の職業が判別できない『月夜のでんしんばしら』は除いて、『鹿踊りのはじまり』では、作者は嘉十と一体化している。すなわち、大正十年の八月から九月までの短期間に、賢治の農夫への態度が、否定的なものから肯定的に変化したということである。極端な言い方をすれば、芸術至上主義者から、農民芸術論者とまでは言えないにしても、芸術と生活の両立を目指す者に変わった、とは言えるのではないか。 ○『どんぐりと山猫』 《をかしなはがきが、ある土曜日の夕がた、一郎のうちにきました。 かねた一郎さま 九月十九日/あなたは、ごきげんよろしいほで、けっこです。/あした、めんどうなさいばんしますから、おんで/んなさい。とびどぐもたないでくなさい。 山ねこ 拝》 ある日突然、こんな葉書が一人の少年の家に舞い込み、その少年がうれしさのあまり《うちぢゅうとんだりはねたりし》たとしてもよい。しかし、人を招待するにしては、なんとも散漫な葉書である。時刻、場所の指定がないのである。山猫は、時刻、場所の指定をしないで、少年にどうやって、そのめんどうな裁判が行なわれるという場所へ来いというのであろう。葉書が葉書なら、少年も少年だ。そんなことには、なに頓着する風もなく、翌朝《ひとり谷川に沿ったこみちを、かみの方へのぼって行》く。あるいは、《山ねこ 拝》とあるだけで、その土地の子供なら、すぐさま思い当たる場所があるのかもしれない、とも考えてみる。ところが、今度は《やまねこがここを通らなかったかい。》と、栗の木に尋ねたりするから、やはり裁判の行なわれる場所を知らないのかな、と思うと、山猫は今朝早く東の方へ行ったよ、という栗の木の答えに、《をかしいな》と言ったりする。自分の中に、或る心積りがなければ、こんな風には言わないだろう。こちらは、ただ、ただ、翻弄されたあげく、栗の木に尋ねたのは、自分の予想を確認しただけなのだ。というところへ落ち着く。そうでなければ、自分から尋ねておきながら、笛吹きの瀧、きのこ、りすのいずれの答えにも少しも耳を貸さず、《まあすこし行ってみよう》とばかり繰り返す一郎の言葉の真意が計りかねる。これでは、山猫の行先を尋ねる場面は、木や瀧やきのこやりすと少年が、あたかも当然のように会話を交わすことの愉快さを考慮しても、裁判が行なわれる場所へ行くまでの、単なるつなぎと思われても仕方あるまい。いったい、作品が何を訴えようとしているのか杳として掴めないのである。 たとえば、厄介な裁判の収集のために、どうして一郎が選ばれたのかということ。そんなことは、一郎の関知するところではないのかもしれない。それならば、山猫の方から、特に一郎だけを選んだことの理由について一言あってもいい。山猫の方が言わないのなら、一郎が尋ねて当然だと思うのだが、それもない。 だからと言って、ここで作品の不備をあげつらったり、作品への不満を列挙したりすることにいかほどの意味があろう。そうではない。本来、作品が備えていなければならないと思われるものが、あたかも過失のようにスッポリ抜け落ちていて、そのことに賢治がまったく気づいていない、気づいていないかのように見える、ということを問題にしたいのだ。と言うのも、『よだかの星』で、「よだか」が死を決意するのは、それだけはけっして受容できない要求を、鷹に叩きつけられたからなのだし、『貝の火』で、ホモイが宝珠を授かったのは、川で溺死しそうになっていた雲雀の子を、ホモイが文字通り身を呈して救った故なのである。つまり、今、挙げた二つの作品に関してだけでも、作者は、作品の中で起る出来事について、ちゃんとその因果関係を描写することを忘れていなかったのである。それなのに、どうして『どんぐりと山猫』には、それがないのか。ここに、この時期の賢治の心理状態を解く鍵がある。 ともかく、かの厄介な裁判なるものが始められる。と言うよりは、どんぐり間の、どんなどんぐりが一番偉いか――を巡るたわいない言い争いである。その調停役が山猫なのだが、この言い争いは鎮まりそうもない。そこで、山猫が一郎に方策を請うわけなのだが、一郎は、《このなかでいちばんばかで、めちゃくちゃで、まるでなってゐないやうなのが、いちばんえらいと》言い渡すよう、山猫に言う。それで、今日で三日目だという裁判も、あっさりと片付いてしまう。 一郎の言葉が、何か高尚なことを言っているようには思えない。いや、鼻っからこのように突き離すことで、看過ごすものがあるかもしれない。存外、作者は大真面目で、一郎の口を借りて、自分の思うところを開陳している可能性だって、なきにしもあらず、だから。 賢治が、自分よりも恵まれていない人間に負い目のようなものを感じていたことは確かである。資質ということもあるのだろうけれど、わたしは大乗思想の影響であろうと思う。 自分だけの救われを求める(と考えている)小乗への批判があるから、自分の方が恵まれていると思ったときに、恵まれていないものに負い目を感じるのだろうと思う。そういう心理的圧迫感を、一気に取り払いたいというような苛立ちがあるから、《いちばんばかで、めちゃくちゃで、まるでなってゐないやうなのが、いちばんえらい》というような、一般的な価値観をただ逆立ちさせたにすぎない、一見、思想的に見えて、感情的な叫びでしかない表現を呼び込んだのである。 だから、間違っても、一郎の吐いた言葉がその場の出任せだ、などとは言うまい。つまり、作者の心情をある程度代弁しているとしよう。しかし、いくら作者の事情を考慮したとしても、裁判が終結するにしては、一郎の言葉は説得力がなさすぎる。それだけに裁判がまるで一郎を持ち上げるためにのみ行なわれたとしか思われないのである。少なくとも、この一郎の言葉が、この作品の主題であるとは思えない。となると、作者は、いったい何に腐心していることになるのか。やはり、作品の構成――現実世界の人間を、ひとたび非現実的な世界(動植物、及びそれに準ずるものを擬人化することによってなっている世界)へと誘い、再び現実世界へ帰還させる――以外には考えられない。 まさか、とは思う。まさかとは、賢治が観想によって、あらゆる現象を無いものと見做そうとするときの過程と、作品の構成がちょうど反対になっているということである。往(い)きて還(かえ)る、仏の往相(おうそう)、還相(げんしょう)のことなども思い浮かんでくる。『どんぐりと山猫』の場合は、往きて還ると言うより、「誘(いざな)って送り還す」と言った方が正確だとは思うが。 『かしはばやしの夜』を論じているときにも、気にかかってはいたのである。柏の木大王に前科九十八犯と罵られて、清作が怒って《あっはっは。九十八の足さきといふのは、九十八の切株だらう。それがどうしたといふんだ。おれはちゃんと、山主の藤助に酒を二升買ってあるんだ。》とやり返すところ、清作の反応が物すごく即自的、肉感的で、大王の言葉に自分の筋力(生活力)で反発しているようにすら感じられる。作者に近い登場人物と言えば、絵描きだが、もし、この清作に作者が自己を擬したとすれば、作者が肉体の復権を計っているとも考えられたからである。 確かに、自然交感といえば、耳触りはいい。でも、そうかな、という気はする。自然との交感に自己慰安を求めるというのは、裏を返せば、人間関係の軋轢に耐えられない精神構造を彼が所有していたということではないのか。 《風の中を なかんといでたるなり 千人供養の 石にともれるよるの電燈》(「冬のスケッチ」第十三葉より) 何か、家人の人と諍いがあって、たまらず表に飛び出した、という感がある。生活の根っ子は父親に押えられており、いくら、賢治が理想論をかざしたとしても、そんなものは生活の論理によって一蹴に伏されてしまうことは目に見えて明らかである。その都度、賢治は自己確証、自分は間違っていないということを、自然、そして、脳裏に展開する物語に求めるしかなかったのだ。自然は、いつも自分を裏切ることがなく、悠然と自分を待ち構えていてくれるからだ。その中でしか、賢治は自己を解放する術を知らなかったのである。 たとえば、栗の木や瀧、きのこ、りす、どんぐり等々と一郎が会話を交わすこととして、あるいは、自然交感というようなことが言われるのかもしれない。わたしには、どうもそれは疑わしい。自然との交感に慰安を求めるというのは、裏を返せば、彼が人間関係の軋轢に耐えられないということだ。動植物と会話を交わすと言ったところで、動植物の会話は作者が考えて言わせているのである。だから、本当は、独り言に近いものなのだ。ただ、彼が、動植物に言わせているのだから、現実の人間相手の時のように、相手の言葉によって傷つくということはない。 これも、一つの厭世の形であるにはちがいない。自分を取り巻く人間関係、世相に背を向けて、自然の中に自己の慰安を求めたのである。――自然は自分を裏切らない――という確信が彼にあったからであろう。 ここに手負いの魂が彷徨していることだけは確かである。 |
| 批評的切片 連載第一回 スーパー・スターとしてのイエス 千石剛賢著 父とは誰か、母とは誰か 1986年4月刊 |
清水鱗造 |
○書かれたものとしての聖書――信仰の次元 「イエスの方舟」が興味深いのは、この集団の生活状況が、追い込まれた個人をうまく吸収できる力があることを示している点にある。興味の集中点は、まず現在の状況によって追い込まれた個人がどういう生きかたを模索するかにある。追い込まれた個人の行く末を調べること、それに現在の状況が映しだされているはずだ。もうひとつ先走っていえば、「大衆意識」の切っ先が現われているはずだ。 聖書を「すべて本当のことが書かれている」と一口に言うことの中には、「自分の受け取り方に誤りがあるとしても、書かれていることはすべて本当である」という意味が含まれている。これは「書かれているもの」と「受容」を画然と分けることである。 例えば「受容」に誤りがあれば、「受容」から立てられた概念をもととする行為にも誤りがありうる。また結果としての明らかな誤りを、別の誤った「受容」から立てられる概念によって正当化してしまうという更なる誤りが起こってくる。言葉を受け取っていくとき、常にこの危険に直面している。 普通書かれた言葉を受け取るとき、自分の受け取り方に誤りがありうるということ、さらに正しい受け取り方をしたとしてもその内容に誤りがありうる、という二重の不審のうちに言葉は受け取られている。さらに書かれたものと受容には必ずズレがあって一致しないという考え方も普通だし、積極的には言葉が含蓄的に表現している見えない価値、無意識に伝えようとする価値を受け取りの経過中に伝えられるという考え方も普通である。だから言葉で表現されたものは、人間全体からみれば限定されているものであって、しかし人間の概念形成能力によって極限の「方向」は示すことができるということである。 信仰の領域は、自分の受け取り方には誤りがあるのかもしれないが、仮に誤りなく受け取れたとしてそのときその内容には誤りがないという領域である。 例えばカトリック教会は聖書の不可謬姓について次のようにいっている。 聖書は神の霊感によるものであるから、従って不可謬である。レオ十三世教皇が教える通り、神の霊感は、事実上の誤謬を排するばかりでなく、(真理そのものなる神が誤謬を示し得ないと同様に)必然的、先天的に誤謬を退ける。といっても、聖書史家の教育程度によって起る単に形式上の、つまり文法とか文章構成法とかいった方面の誤りはありうる。(カトリック系の新約聖書訳者の聖福音書緒言より) しかし、言葉というものを客観的に考えれば、それ自体が誤りのない極限に近づくということで常に本当のことには届かないということは前提なのであるから、この視点において信仰はありえないということになる。しかし、すくなくとも言葉の真実に対する漸近線を構成する意思は現実にあるということは考えられる。信仰は絶対を措定しなければ不可能であるが、そのことを前提としたうえで、一方で常に言葉としての経典を分解し、この意思にできるだけ近づくという作業も行なわれる。例えば言葉を発したイエスの意思に極限的に接近していくことである。 引用した《真理そのものなる神が誤謬を示し得ない》というところに表われているように、先に不可能を設定してしまえばその上にフィクションを構築することもできる。しかし、言葉に対する考え方においても、聖書の内容は本当は反構築の立場に立っているように思われる。言葉の含蓄する内容に対する受容の漸近線について認識しているように思われる。 ○理路の典型 「イエスの方舟」のライフ・スタイルは、まず通常的な家族を捨てるところからはいっていく。 聖書には「仇はその家の者なるべし」(マタイ10-36)というみ言葉があります。このことを突っ込んで深くいきますと、たいへんなことになっちゃってね。まず、仇の鉾先にあげられる者は、父とか、母とか、兄弟とか、こないになっちゃうんです。 これをまともに説教したら、えらいことになります。まともに説教したつもりはないんですけれども、ちょっと触れたのが、あの事件(イエスの方舟事件)のとっかかりみたいになっちゃったんですね。もちろん、親が悪魔だと言いきったことはないんですけれども、それに等しいような状態になっちゃったんですね。けども、もちろん、聖書の真意をなお深く突っ込んでいきますと、「仇はその家の者なるべし」といわれても、これは、父や、母や、兄弟に留まるのではなくて、実は己れ自身ということになるんですね。いちばんの仇は己れ自身。いうなら、悪魔の巣窟は己れだと、こないなるんですね。(168ページ) ルカ伝にこうあります、「だれでも私のもとに来て、父と母を憎み、妻、子、兄弟、姉妹、自分のいのちまでも憎まないならば、私の弟子であることはできない」(ルカ14-26)と。これを端的にゆうと、イエスの弟子になるためには、父と母を憎まないかんと、こうなっちゃうんです。これをまともに取られたらどうにもならん。調子悪い。(略) ここでは「父と母を憎む」という訳ですけれども、創世記二章だと、「憎む」というのは「父母を離れて」と、こうなるんです。つまり、幻想的な人間関係は真実とするなということなんです。親と子というのは、幻想的な人間関係なんです。つまり、人間が勝手にそういうふうに認識しているだけなんです。人間という存在の現実じゃありません。(略) だから、この「憎む」ということは、けっして幸せにしない人間関係の認識を離れるということです。自分の母、自分の父、自分の子、他人の子、こういう発想は人間を幸せにしません、けっしてね。そういう意味ですよ。(218〜221ページ) こういう考え方には、家族の存在がすでに自分を幸福にしていない、俗にいって家族運が悪い、しかし血を分けた者、どんなことがあっても愛さなければならない。しかし、憎しみが湧いてくる。という二重の強迫的枠組を解消する理路がある。被迫害者にとって当面必要なのは自分のアイデンティティーを保つことである。迫害が厳しければ厳しいほど、 被迫害者の心理の真相に障害が及んでくる。聖書は被迫害者の心理について精通しているから(被迫害者としての時間の集積をもっているから)、被迫害者のアイデンティティーを保つ理路が用意されている。 加担というものは、人間の意志にかかわりなく、人間と人間との関係がそれを強いるものであるということだ。人間の意志はなるほど、撰択する自由をもっている。撰択のなかに、自由の意識がよみがえるのを感ずることができる。だが、この自由な撰択にかけられた人間の意志も、人間と人間との関係が強いる絶対性の前では、相対的なものにすぎない。(吉本隆明〈マチウ書試論〉より) 家族内でどうしても迫害され、家族を憎むことしかできない。それが苦しいから家族から出てしまった人を癒やすのはその二重の強迫的枠組を解体してしまうことしかない。吉本の「関係の絶対性」は二重の強迫的枠組そのものである。この概念を反転すれば、例えば家族という関係に基づく秩序に反抗する理路が得られる。阻害するものを正面から糾弾するときの、二重の強迫的枠組を除く理路が得られるのである。《秩序にたいする反逆、それへの加担というものを、倫理に結びつけ得るのは、ただ関係の絶対性という視点を導入することによってのみ可能である。》(同前)家族という秩序のなかにいるのに、自分だけはその秩序からただ阻害されるだけとしたら、そこから離脱するまでである。しかし簡単にはいかない。現実的にほとんど離脱できない。というとき、もし、本当はすべてを捨てて離脱してもいいんだという考えをもちつつ離脱しないならば、自分を定位することができる。関係の絶対性ということはまた時間的には「過程」である。阻害という時間的な一点を「過程」に位置づけることができる。 だから「イエスの方舟」における家族離脱者は、理念としてその根拠をもっているともいえる。この集団生活は過程的なものであり、家族離脱も過程的なものであると考えられれば、生活におけるアイデンティティーは保たれる。 ○「イエスの方舟」の生活 聖書が人間の心理に通暁していて、サイコセラピーさらに意思の拠点づくりに役に立つということが入口としたら、そこから先は「イエスの方舟」はどのように考えているのだろうか。実は現在の状況はその入口に集中的に現われている。後は「イエスの方舟」の個個の生活の問題になってくる。彼らがどんな生活をしているかは、別に興味はない。マスコミの「イエスの方舟」の追い方、報道の仕方の問題は芹沢俊介著『「イエスの方舟」論』がくわしく批判しているが、入口の向こうを見ようとするのにそれほどの意味は見出せない。入口には、生活するのに必要な概念の糸口が出揃っているはずである。 私を支えつづけているのは、ある意味では〈十字架の死〉と〈復活〉。それと〈マリアの名〉(神がインヌマエルとして、人類の中に人格的に現われ給うときにかかわる受的存在者の人格の実質を指す)と処女降誕。これは一つになりますけれども、この四つとも三つともいえる在り方が私を支えているし、本質的な意味でいいますと、イエスの方舟を支えています。この在り方に支えられながら、主のみ言葉を各人各人の場で自己のすべてをかけて生活しているのが、イエスの方舟の生きざまです。(81〜82ページ) これらは多くのキリスト教信者の考えとそれほど変わりがあるとは思えない。しかし、千石剛賢の日常的な実践の切り口は現在的である。一口にいえば教義の現在的な解体ということになるのだが、欲望を扱うとき陰湿感がないし、開かれている印象をもたせる。現実の秩序に反抗する契機を持ち続けながら生活することを可能にさせる理路が聖書にはあるのだが、その状態をつくるのはとても難しいだろう。制度に和合していったキリスト教の在り方には、何の魅力もない。 イエスが十字架にかかられたあの客観情勢は、人間としては、最悪の客観情勢です。(略) ところが、これほどひどい客観情勢の真っ只中で、主イエスはパラダイスとおっしゃっているんです。(略) 極端なことを言いますと、金がなくなっちまって生活に困るという状態が出ても、客観が変わるという意味はすこしも変わらないんです。ご利益宗教的なもんやったら、どうしてもお金ができんと困っちゃう。客観が変わらんことになってしまう。すると、その祈りは虚しいと、こうなるんですけれど、私自身の場では、祈りはけっして虚しくならないんです。なぜならばご利益宗教的な客観情勢の好転を願ってませんから。金ができることなどは考えちゃいないですからね。(246〜247ページ) ここまで、聖書の解釈をポップに生活意識に入れることが可能になれば十分であるような気がする。十字架上のパラダイスというのを陰湿にではなく、生活上に取り込んでいる。 あなたたちがおそわったように、「姦通するな」ときめられている。しかし、私はいう、色情をもって女を見れば、その人はもう心の中で姦通したのだ。(マテオ5-27) この句に対する千石の解釈は《イエスには、要するに、性欲の悩みというのはなかった。 健康な男子なのに、なかった。その理由は〈原罪〉がなかったから。(略)これは、とんでもない言葉ですね。こんなことが平然と衒いもなく偽善でもなく言えるのは、〈原罪〉がなかったイエスしかないはずです。》(201〜202ページ)ということである。イエスという彼岸を措定し、それへの漸近線を解釈とするということである。 一方、吉本隆明の〈マチウ書試論〉から引用してみる。《この性に対する心理的な箴言は異常なものである。渇望をもって女をみるものは既に心のなかで姦通を行ったのだという性に対する鋭敏さは、けっして倫理的な鋭敏さではなく、病的な鋭敏さである。姦通してはならないという掟は、ユダヤ教の概念では、社会倫理的な禁制としてあるわけだが、原始キリスト教がここで問題にしているのは、姦通にたいする心理的な障害感覚であることは明らかだ。(略)この性についてのマチウ書のロギヤは、決して倫理的なものではなく、むしろ本当は倫理観の喪失以外のものではないのだが、もし、このロギヤを倫理的なものとして受感するならば、人間は、原始キリスト教によって、実存の全領域を脅迫されるよりほかないであろう。》 吉本はこの句を真正面から解釈している。信仰の領域にある千石の考えと違って、マチウ書の成立と原始キリスト教とユダヤ教の対立の側面から、どうしてこういう言葉がイエスから発せられたのかを考えている。聖書をまともに考えるためには、どうしてもこういう手続きが必要なのだが、信仰の領域では、どうしても人間の全実存を脅迫できるような絶対的なものを措定するしかない。さらに向こうに投げ返すしかない。 その絶対的なものから構築することは不可能である。絶対的なものは現実に存在しないのだから。だから現在的な信仰の課題として、絶対的なものを措定したら、瞬時にそれを解体するという手続きが必要で、色合いを分けるのは絶対に対する漸近線をつくる方法ということになる。スーパー・スターとしてのイエスをポップにとらえて、生活するという「イエスの方舟」の遣り方が、現在的な信仰のひとつの形を示しているのは確かだと思われる。 ところで、「絶対的なものから構築するのは不可能である」という立場からみれば、「絶対的なもの」が丈夫から設定された瞬時に、すでに解体が始まらなければならない。そこから向こう側へ簡単に踏み出すのが信仰かどうかも問われなければならないが、こちら側にいる人間としては、向こう側に立てられるものは全否定の立場をとらねばならない。「イエスの方舟」が家族崩壊の現在のかたちの緊張の吸収装置という機能になりえていることから、逆に現在の状況をみなければならない。このことが重要だと思う。キリスト教の細かい教義など瀬戸際に立たされている者にとってどうでもいいのだ。当面の平衡と、新しい場面に出ていく思想をポップに吸収できれば、そこが足場になりえるのだ。< *聖書の引用は『新約聖書』(昭和32年発行 フェデリコ・バルバロ訳)から。 |