詩 都市 批評 電脳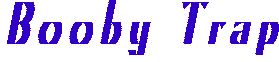 第8号 1993.5.30 206円 (本体200円)〒154 東京都世田谷区弦巻4-6-18(TEL:03-3428-4134:FAX 03-5450-1846) 編集・発行 清水鱗造 編集協力:パニック・システム Special thanks to rapper, pmd and BBS Panix 5号分予約1000円 (切手の場合72円×14枚) |
詩 都市 批評 電脳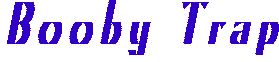 第8号 1993.5.30 206円 (本体200円)〒154 東京都世田谷区弦巻4-6-18(TEL:03-3428-4134:FAX 03-5450-1846) 編集・発行 清水鱗造 編集協力:パニック・システム Special thanks to rapper, pmd and BBS Panix 5号分予約1000円 (切手の場合72円×14枚) |
| バタイユ・ノート 2 バタイユはニーチェをどう読んだか 連載第1回 |
吉田裕 |
1、ニーチェの像をどう引き出すか シュリヤの詳細なバタイユ伝によれば、バタイユは一九二二年頃、ニーチェにはじめて接したらしい。古文書学校をでる二十五才の頃である。最初の本は『善悪の彼岸』であって、次に『反時代的考察』がくるが、それらは決定的な読書体験となる。後に〈なぜこれ以上書こうとするのか。私の思考――私の思考のいっさい――がこれほど完全に、これほどみごとに表現されているというのに〉と書くほどである。ところでバタイユが哲学から受けた影響を言うならば、もうひとりヘーゲルの名をあげなければなるまい。ヘーゲルに決定的な形で出会うのは一九三三年にコジェーヴの講義にでるようになってからであるが、このドイツ観念論哲学の完成者について、バタイユは、〈ヘーゲルは自分がどれほど正しいか知らなかったのだ〉と言っている。これらの引用から、バタイユが二人の哲学者から、きわめて強い影響を受けたことがわかる。しかしながら、ニーチェがヘーゲルに対する批判者であったことから推測されるように、ヘーゲルからの影響とニーチェからの影響は、葛藤なしに両立しうるものではなかった。ある批評家は、バタイユはヘーゲルに不満を持つとニーチェの立場から批判し、逆にニーチェに不満を持つとヘーゲルの立場に移ったと言っている。バタイユはニーチェについては、〈ニーチェには弁証法が理解できなかった〉と批判し、またヘーゲルのことを〈老いぼれ坊主〉と罵倒したりした。 けれども、〈私は哲学者ではない。私は狂人だ〉と言うような人間にとっては、ニーチェのほうがより身近に感じられていたと言えるかも知れない。バタイユを読んでいて節目々々でより直接的に現れるのは、ニーチェの名である。彼のファシスム批判はニーチェ的な原理に基づいているし、彼が占領下の困難な生活を切り抜けるのは、全編ほぼニーチェ変奏曲というべき、『無神学大全』を書くことによってである。戦後においても彼は、最大の問題となったコミュニスムに触れるにあたって、〈今日の世界において、コミュニスムとニーチェの姿勢以外に、どんな姿勢も受け入れることはできない〉(「マルクシスムの光によってみたニーチェ」)と言うのである。だからバタイユにおいてニーチェの像をたどることは、ただ彼の思想形成の影響関係のひとつを探ることなどではなく、彼の根底を照らす視点となるだろう。 しかしながら、バタイユがニーチェをどう読んだかを明らかにすることは、限定された小規模な作業のように見えながら、実際はそれほど簡単ではない。バタイユがニーチェから受けた影響を、彼の書いたどの著作にみればよいのか、焦点が絞りにくいのである。バタイユを少しでも読み込めば、彼がニーチェの影響を深く受けていることはすぐ見て取れるが、しかしそれがどこに具体的に現れているかを特定することはむずかしい。『ニーチェ論』と題した一冊があるが、半分は彼の日記であり、収録されたいくつかの論文も個別に発表されたものを集めたものであり、これを一冊読めば、彼のニーチェ理解がくまなくわかるというものではない。ニーチェの像はバタイユの全体にわたって、広く深く浸透し、バタイユの骨肉と化していると言うほかない。そのようなときどんな方法によって、この影響関係をとらえることができるか。私には平凡な方法しか思い浮かばない。つまりバタイユがニーチェを主題にした論文、あるいはニーチェについての言及がある論文をともかく読みつないでみることである。 この方法には欠陥があることはわかっている。ニーチェの名を冠された部分だけを取り上げると、トピック的な部分だけが強調され、全体に浸透して基底をなしている部分をかえって見逃してしまうことがないとはいえないという点である。これはその通りだが、個別の論文は目につく露岩にすぎず、それはただきっかけであって、そこから基底のほうへ下っていく通路を常に開いておくことを自分に言いきかせるほかあるまい。そこで完結したガリマール版の全集から、題名中にニーチェの名を含むもの、論中にニーチェに関する言及の多いものを、目につくかぎりで抜き出してみると、次のようになる。 1、「ニーチェとファシストたち」、三六年(六〇枚) 2、「ニーチェ・クロニック」、三七年(四〇枚) 3、「ニーチェの狂気」、三九年(一五枚) 4、「序文」(『ニーチェ論』)、(四〇枚) 5、「ニーチェ氏」、(四〇枚) 6、「頂点と衰退」、(八〇枚) 7、「ニーチェと民族社会主義」、(一〇枚) 8、「ニーチェの内的体験」、(一〇枚) 9、「ニーチェの笑い」、(二五枚) 10、「ニーチェとコミュニスム」、(二〇枚) 11、「ニーチェとイエス」、(六〇枚) 12、「ニーチェと禁制の侵犯」、(四五枚) 13、「ジッドとヤスパースによるニーチェとイエス」、(四五枚) 14、「マルクシスムの光のよって眺めたニーチェ」、(二〇枚) 15、「ニーチェとトーマス・マン」、(四五枚) 16、「ニーチェはファシストか?」、四四年(一〇枚) 17、「ジッド・ニーチェ・クローデル」、四六年(一〇枚) 18、「ニーチェとウィリアム・ブレイク」、四九年(三〇枚) 19、「ニーチェ」、五一年(一〇枚) 20、「ツァラツストラと賭の魅惑」、五九年(一〇枚) これらは全集の番号の若い順に、また収録順に並べたものである。執筆年、あるいは発表年がわかっている場合は末尾に示した。また()内の数字は翻訳した場合に四百字詰めの原稿用紙でどれくらいの量になるかを概算で示したものである。1と2は実は連続したひとつのものである。だから以後二つを合わせて、「ニーチェとファシストたち」と呼ぶことにする。4から8は一九四四年刊の『ニーチェ論』からで、そのうち4、5、6が本文、7、8は補遺である。10から12は、「呪われた部分」の一部として構想されたが生前には刊行されなかった『至高性』からのものである。13から15は全集では付録として扱われているが、13は11の、14は10の、15は12のもととなった原稿である。従って10から12は一九五二、三年頃の執筆と推測される。16以下は戦後の補遺的なニーチェ論で、そのうち16は7のもとになった原稿である。特に言及しなかったものは、独立した論文として扱われている。 バタイユにおけるニーチェというテーマで書くためには、これらの論文を主なる対象にすることになる。しかし、それには欠落している部分があるので、それをあらかじめ明らかにしておく。それはここには、彼がニーチェを読みはじめた最初の時期のことを示す論文がないことである。標題から推測できようが、彼のニーチェ論はいきなりファシスム批判の文脈の上で現れる。それ以前の彼のニーチェ読書は、この一覧からは必ずしもうかがうことができない。 ほかのところから知りえたかぎりでは、バタイユは一九二〇年頃から徐々に信仰を失っていったが(「自伝ノート」では、ロンドン旅行からの帰途、ワイト島のベネディクト派の修道院に滞在中に突然信仰を失ったと書いているが)、そのかわりにニーチェの像が彼のうちに食い込んでいったように見える。そのときニーチェはバタイユに、神の概念、少なくともキリスト教的な神の概念に頼らずとも、神的な体験が可能であること、そのゆえに神の名は拒絶されるべきであることを教えたのではないか。バタイユはこの示唆に従って、少しずつキリスト教的な思惟の方法と用語から抜けでるのである。 ただこの時期のことについては今は十分な証明ができないので、保留するとして、ともあれこれらの論文を読んでみる。すると私はいくつかの印象を受ける。ひとつにはニーチェがかなり戦略的、実践的に読まれていることである。そしてそのためか、時期によってバタイユにおけるニーチェは、かなり違った様相を見せる。変化は戦争以前、戦争中、戦後の時期にほぼ対応している。 戦争以前のニーチェ論は、標題から明らかなように、ファシスム批判のために書かれている。ニーチェはドイツ・ファシスムの思想的な先行者のひとりとして喧伝されたが、バタイユからみればそれはニーチェを歪曲するものであった。だから彼はファシスム的なニーチェ像を批判し、ニーチェを奪い返さねばならなかった。そしてそれがバタイユにとってはそのまま反ファシスム闘争の重要な支柱のひとつであった。 これにくらべると戦争期のニーチェ理解は、内在的なものだといえるかも知れない。フランスはドイツ軍の占領下にあり、バタイユには「社会科学研究会」も「アセファル」もなく、しかも結核を発病して療養の身であって、彼は自分の内部をのぞき込むほかなかった。この時期のニーチェの像は神秘主義的であり、「内的体験」と深く絡みあって現れる。 戦後のニーチェ論で目につくのは、コミュニスム批判の文脈で読まれたニーチェである。彼はこの〈戦後最大の問題〉に取り組むにあたって再び、ニーチェの視点に拠っている。それ以外では、彼は他の作家思想家のニーチェ論を批判し、また以前のニーチェ理解を反すうして、多面的な展開を見せているが、私はかならずしも戦争以前、あるいは戦争下のニーチェ論のような緊張を感じない。戦争は終わったこと、また一九五〇年くらいからすでに彼の健康が衰えはじめていたことが原因になっているのだろうか。 とりあえずこのように分類される彼のニーチェ像の諸領域のなかから、他の領域との接点を見失わないよう留意しながら、私はまず戦前のニーチェ像、すなわちファシスムと争った時期のニーチェ像を問うことにする。若年の出会い以来神の存在に変わって刻み込まれたニーチェの像は、この時期に最初の現実的試練を受け、次にくる神秘主義的なニーチェと対になって彼のニーチェ理解の最大の振幅を形成し、その動揺のなかにバタイユ自身の思想の根底をも覗かせるように思われるからである。 |
| 化石 |
辻仁成 |
|
預かったもの
|
辻仁成 |
|
| 犬の名前 |
倉田良成 |
|
| ころげる石 |
清水鱗造 |
|
| 発火 |
清水鱗造 |
|
| ともに来るべきものの姿 |
坂本浩 |
- Shapes of things before my eyes, Serve me to despise (`Shapes of things' the Yardbirds) 【序説】 コンピュータそれ自体は、あるテクノロジーの結果以外のものではなく、その意味では特別革命的でも、神秘的でもない。もし、それがいかにも革命的にみえるとすれば、革命的なのはそれを生んだテクノロジー自体であり、それが、神秘的にみえるとすれば、コンピュータを使うことになる人間と、それを生んだテクノロジーとに、一見越えがたい距離があるということに過ぎないだろう。つまり、それを実現したテクノロジーからのインパクトがもしなければ、コンピュータはたんなる「もの」であり、その「もの」によって作られる環境は、たんにそれ以外の任意の環境と比較されるだけですむはずである。たとえば、内燃機関を内燃機関として問題にするのではなく、車や製鉄所を問題にするように。 われわれが現在コンピュータに向ける視線は、たとえば「都市」に向けるそれに、似ているといえるかもしれない。都市とは、徹底的に唯物論的な存在であるのだが、われわれは、程度の差こそあれ、どこかで都市を唯物論的に把握しようとする姿勢をあきらめてしまう。そのとき、われわれが求めるのがイメージなのだ、といったら言いすぎになるだろうか?安易な文化記号学的都市論に、なぜかいまだに需要があるのは、そのためではないだろうか。確かに都市は、常に他の何かを表象し得るし、恒常的なイメージの供給源になり得るだろう。しかし、それは都市自体にはなんの関係もないことである。われわれは、確かにしばしばそれらのイメージに魅せられるが、魅せられたままでは「都市」そのものは、ついにわれわれの視界には入ってこないに違いない。カエサルのものをカエサルに返すのはよい。だがそれは、カエサル以外のものにしか値打ちがないのだ。時として都市が生み出したイメージと戯れることは許されるが、絶対に避けなければならないのは、イメージを語ることで都市そのものを語ったような気になることである。 いうまでもなく「似ている」というのはこのことであり、現在の、コンピュータとそれに代表される現代の高度情報化社会についての言説にも、そのままあてはまる。が、実は、事態はわれわれのこのような認識よりも、遥かに進んでしまっている、というべきだ。すでに変化は、われわれのイメージ形成能力が必然的に立ち入れないところで、起きるようになっており、仮にあるイメージが供給されたにしても、われわれはむしろそのイメージにいらだちを感じることが多くなっている。J.G.Ballardはいう。 “テクノロジカル・ランドスケープの人間住人は、もはや、アイデンティティの境界領域へ近づく鍵を与えてくれる鋭い標識ではなくなってしまった。同僚の有閑マダム、フランシス・ウェアリングが楽しげにそぞろ歩き、くぐり抜けるスーパーマーケットの回転ドア、アパートの裕福な隣人とのみみっちい口喧嘩、この穏やかな郊外群落が抱くすべての希望と夢想は一千回の不貞にひからび、不変にして不動の均整をそなえた高速道路の土手の堅固な現実の前に、駐車場の車寄せの確固たる存在の前に敗北してしまったのだ。” われわれは明らかに大きな変化のなかにいる。だが、いままでのような感じ方では、われわれはその変化を感じることができないのだといってもよいかもしれない。この事態に直面したバラードが、その中期三部作において採用した方法は、それ自体興味深いものだが、ここではそれはしばらくおこう。要するに、たとえば、列車がこれまでよりはるかに速いスピードで目の前を通りすぎてゆくとか、いままで見たこともない巨大な建造物が建っているとか、それに類するものによっては、われわれはテクノロジカル・ランドスケープを感じとることができなくなった、ということなのだ。SFはかつて、疑似科学が生み出したさまざまな発明品によって、未来のイメージを供給した。しかし、SFガジェットは、ほどなく、ある程度失笑を買う覚悟がなければ提出できない遊び道具に転落した。いまやそれらは単に馬鹿々しいだけである。 コンピュータを始めとする最新のテクノロジーは、テクノロジー自体を洗練されたものに変え、それに特有のイメージを完全に追放するに違いない。おそらく、テクノロジカル・ランドスケープは、日に日に牧歌的になって行くだろう。いや、そういう予測は、いくらでもはずれる可能性があるのだ。テクノロジカル・ランドスケープとは、つまり任意の「ランドスケープ」のことなのである。 □ テクノロジーは、風景のようなマクロのレベルにおいて、イメージの権威を失墜させる。が、「同僚の有閑マダム、フランシス・ウェアリング」に目を向けてみるとどうだろうか。 《隠喩》‐メタファー‐とは、あるものごとの名称を、それと似ている別のものごとをあらわすために流用する表現法である。われわれはこれを、既知のイメージの組み合せによって未知の事象を形象化する方法であると言いかえることができるだろう。そして、われわれは、馴染みが増すにしたがい、コンピュータが、われわれ自身の有効なメタファーとなり得ることに気づきはじめているようである。 このことは、コンピュータ・サイエンスの進歩とは、たとえば、ありうるAIがどのようなものか、といったことには直接関係がないように思える。なぜなら、最新の成果は広く流通しないからだ。一方、われわれは、われわれ自身を、ネットワークの一部として他のコンピュータに繋がり、割り込み処理を行う学習するコンピュータと看做すことにすでに慣れてしまっている。事実、コンピュータ技術者の間では、人間の動作や状態をコンピュータ用語で言い表すのは、比喩の段階を越えて普通になっているようだ。事実、ただ一点、誰がこのシステムを作ったか、を不問にすれば、人間をよくできたオペレーティング・システムと看做すのになんら不都合はない。 これは、やはりバラードがいうところの「極端な状況における極端なメタファー」にあたるかもしれない。人間の比喩にコンピュータを使うことの根拠は、双方がたがいに似たところのあるシステムであるということにかかっているが、いったい、システム以上に比喩がふさわしくないものがあるだろうか?ここでも、われわれはイメージの徹底した不在に立ち会わなければならないだろう。なぜならそこではイメージしえない(してはならない)ものが、イメージしえないものの比喩に使われるからである。 (多くの知能を持った、また持たないにしろ高度な情報処理能力を持ったコンピュータ - たとえばHAL9000 - を描くのに、そもそも擬人化がなされているということはもちろん注意すべきだ。それらの描写の多くは、ここで想定している場合とは逆に、すでにある人間のイメージをコンピュータにあてはめたものだといえる。二つの相反する流れがあるのだ。) □ コンピュータが、テクノロジーの結果として、すでに現実に存在する以上、ありうる叙述に必要なのは、まず、歴史であり統計であり、マニュアルであろう。そうでなく、経験によって、また経験を共有可能にすると信じられているメディア上のあらわれによろうとするなら、われわれは、それについて根拠のない曖昧なイメージ以外のものを得ることはできないだろう。テクノロジカル・ランドスケープの特徴がイメージの不在にあるとすれば、われわれは、われわれの意図にかなうことばを、そこから生みだすこともできまい。実は、イメージの不在とは、いいかえればシステムの顕在化でもある。ここにおいてあきらかになるわれわれの意図とは、つまり、システムのかたちを(いや、システムが目に見えるようなかたちを持っていないことはいうまでもない)を、描き出すということであるのだが。 まあよい。さしあたり、われわれは、コンピュータの周囲を経巡り、それらの場所にばらまかれてきたイメージのうさんくささを、攻撃することしかできないかもしれない。すでにわれわれは、共に来るべきものの姿を、それが周囲を多いつくし、すでにあった秩序にとって変るまで、われわれの目からそらそうとするのが、他ならぬイメージであることにも気づいているのだ。 共に来るべきものとは、おそらく「もの」そのものではない。それは、既に組み上げられたものの秩序をほぐし、新たな秩序へと組み上げるその効果それ自体によって、ものとなるような「もの」ではなかろうか。 |
| 編集中記+α |
本号はBBS Panixの協力を得て、いろいろなtextfileを受け渡しする実験ができた。これから準備して、さらに投稿をパソコン通信でできるようにしたいと思っている。 本号の原稿はすべてフロッピーディスクだった。編集段階では組みだけが手作業になるので、時間の節約にもなる。 具体的にどんな実験だったかというと、pmd氏のところにあるレーザプリンタで、印字をよくするために僕のもっていないソフトウェアでレイアウトする必要があった。 始まりはBBS Panixに僕が〈DTP志向〉というノートを作ったことだった。いろいろrapper氏、pmd氏と話していくうちにレーザプリンタを使用させてもらうことになったわけだ。まず、テキストを電話回線で茨城県に住むrapper氏に送った。テキストを送るためにLHAとishというフリーウェアを利用した。手元に書き手の原稿がくるたびに送り、それをrapper氏がレイアウトしていく。rapper氏がpmd氏に電話回線で一部分を送り、それをテスト印字したものをpmd氏からFAXで送ってもらった。 5月23日日曜日、BBS Panixのホストコンピュータがあるpmd氏宅に集まり、印字プラス宴会ということになった。 ところが、6月初めに僕の買ったレーザプリンタが家に届くことになっていたのだが、予定より早く23日に届いてしまった。これですべて、僕のところでできることになってしまった。ためしにそれまでできていた部分をpmd氏のプリンタですべて印字してみた。ほんとうにrapper氏、pmd氏にはお世話になってしまった。23日は楽しい宴会になった。 246沿いのバス停留所で待ち合わせていた。僕はワインとウィスキーを持って、待ち合わせの場所に着いた。両氏は缶入の飲み物を路端に座って飲みながら待っていた。彼らと僕とは、およそ一回り年齢が離れている。その前にrapper氏が会っていたSwanSong、progeny夫妻も合流した。pmd氏宅ではrapper氏のもってきたビートルズの珍しいCDを聞いたりしながら、話がはずんだ。爆発的に僕の知らないロックグループの名前が飛びかっていく。ソフトウェアの会社だけあって、マシンがいろいろと揃っている。 村上春樹の「1973年のピンボール」は、ピンボールマシンを有効に使った小説でマシンへの執着があるが、この集まりのメンバーはマシンを触ることの喜びを知っているというところに共通点があるのかもしれない。そのなかに、音楽、車、スキー、漫画、文学、科学全般などの楽しみを自在に滑り込ませる。 SwanSong、progeny夫妻が先に帰り、夜中になるとモナコでやっているF1レースをみた。rapper氏の車で246をとばし家に着くと消音してレースの続きを見た。トップをきっていたシューマッハの車はスピンしていた。 |
| 「棲家」について 2 |
築山登美夫 |
ところで北川透は評伝『鮎川信夫――路上のたましい』(以下、「評伝」と略記)への書評で、鮎川の徹底した私生活の隠匿ぶりにふれて次のように述べている。 《このことのうちに、どこかわたしたちの了解を拒む、鮎川信夫の人間観あるいは家族観の毒素のようなものが、潜んでいるような気がしてならない。むろん、彼が亡くなった時に興味本位の話題になったようにレベルで言うのではないが、わたしはそこに何か暗いおぞましきものすら感じる。》(「戦後詩への親しい隔たり」――「新潮」93年2月号) ここで「人間観あるいは家族観の毒素のようなもの」「何か暗いおぞましきもの」というつよいことばで云われているのは、鮎川がその「棲家」――30年にわたる夫人との結婚生活の存在を、どんな親しい友人にたいしてすら匿しとおしたばかりでなく、夫人を母や妹、甥などの親族に一度も対面させなかったという、評伝で明らかにされた事実に象徴される彼の生き方にたいしてなのである。北川はつづけて《他者の容喙を許さないこの翳りこそが、戦後詩人鮎川の深々とした個性であり、魅力なのだと思う。》とし、そしてこの「毒素」を無化したところに、あるいはもっとつよく云えば無化するために書かれたとも思われる(北川はそうは云っていないが、わたしにはそう受けとれる)「評伝」にたいする異和を表明して書評を終えている。 わたしもこのよく調べられた「評伝」にたいしておおよそ同じ感想をもつが、その生涯を精査し作品とのかかわりを公正に記録しようという意図によって、わたしたちに鮎川のもつ「毒素」に気づかせてくれたのも「評伝」なら、結果的にその「毒素」をならしてしまおうとしているのも「評伝」の記述なのである。また作者は著作のきっかけになったとみずから「あとがき」で述べる《その(鮎川の死の――註)すぐ後に、僅かな人しか知らなかった英米語文学者最所フミさんとの結婚生活が話題に上り、そこだけを大きくとりあげて、二、三の雑誌に書かれているのを知った》という「二、三の雑誌」に掲載された文について、まったく言及していない。だがわたしの知るかぎりでは、これらはともに個性とモチフの横溢した書きぶりで鮎川にせまっていて、とうてい無視できるものではないはずなのであった。 その一つは「別冊文藝春秋」87年春号の河原晉也「幽霊船長」、及びそれにつづく一連の作品(著者急逝後、同題の河原晉也遺稿集〈87年11月〉に収録)、もう一つは「試行」67号(87年11月)の吉本隆明「情況への発言――ひとの死、思想の死」(のちに「追悼私記」〈93年3月〉に収録)である。 このうち「幽霊船長」はその文の表面上の誇張癖、臭みが気になるが、よく読みこんでみれば、この作者が生活の辛酸をなめつくしたはてにたどりついた、透明に砕けた心の自在さがそこに一貫して流れていることに気づき、鮎川のプライヴァシーをあばいたとみられる内容を、自己表出性のつよいものにしていることがわかる。鮎川の20年来の「最低の弟子」を自称する河原は、死後「棲家」を探訪したおりのようすを次のように語る。 《薄暗い茶の間を抜けて踏み込んだ、彼の寝室兼仕事場には、縦横に蜘蛛の巣が張りめぐらされていたのである。いかつい寝台の枕辺には、何たることか、匙で掬えるほどの埃が積もっていた。戦慄して立竦む私の目に、カビくさいベッドに横たわる鮎川の幻がちらつく。彼はここで、この棺桶みたいなベッドに眠っていたのだ。》 まだ引用したいところだが、瀬尾育生の詩「棲家」には、すでにこれをふくむ「幽霊船長」のディテールが引かれている。 古着袋にクッションをのせただけの安楽椅子のうえでわたしの体が 沈み始める。わたしは二人だ。もう一人のわたしはついさっき塵埃 袋をぶらさげ傘をさして外へ出ていった、とその人は言う。 「幽霊船長」が引かれたのは、そこで鮎川の私生活があらわにされることによって、さらにふかく匿されたからであり、そのことが詩のイメージと思想の形成に矛盾をもちこむからだ。 河原も、「評伝」の作者牟礼慶子も、夫人にインタヴューを試みながら、申しあわせたようにかんじんなことはきいていない。たとえば鮎川の「棲家」に《縦横に蜘蛛の巣が張りめぐらされ》、寝台の枕辺には《匙で掬えるほどの埃が積もっていた》のは、すでにながく彼がそこに不在だったからではないのかとか、死後に名のりで、牟礼との会見にあたっては戸籍謄本を持ってあらわれたのはなぜなのかとか、最所が50歳になろうとする年になってなぜ入籍しなければならなかったのかとか、そしてなによりも結婚の事実を隠匿しつづけたのはなぜなのかとか……。そしてまもなく夫人も亡くなってしまう。もはやだれも鮎川の結婚生活の証人はいない。そのことがつよく印象づけられるのは、それが鮎川における詩と対象的現実の関係によく似ているからなのである。 |
| 塵中風雅 (五) |
倉田良成 |
貞享三年(一六八六)から同四年の初めにかけて、江戸にあった芭蕉はこれといった旅らしい旅もしていない。上洛の希望はたびたび洩らしているものの、それも計画だけに終わっている。そしてこの間、尾張鳴海の人寂照(知足)宛書簡がやや多いのが目につく。知足。下里氏。のち下郷氏。屋号千代倉。通称金右衛門、勘兵衛。字吉親。別号蝸廬亭。妻の死を契機に剃髪し、寂照湛然居士を名乗る。寛永十七年(一六四〇)に生まれ、宝永元年(一七〇四)沒。享年六十五。尾張鳴海に醸酒業を営む富豪であった。はじめ貞門・談林を遍歴したが、貞享二年四月ごろ「野ざらし」の旅の帰途にあった芭蕉を迎えて入門。以来芭蕉の上方往反のつどこれを迎えて手厚くもてなすとともにその指導を仰ぐ。鳴海蕉門の中心人物であった。俳書のほか、当時の記録として『知足斎日々記』が貴重である。温厚篤実な信仰人にして才のある人であったようだ。 この貞享期、残されている寂照宛書簡としては、貞享三年閏三月十六日付、同年十月二十九日付、同年十二月一日付、貞享四年正月二十日付、同年春ごろ、そして寂照との再会を果たすことになる同年十一月二十四日付の計六通である。このうち、貞享三年十二月一日付のものについて見てゆきたい。以下全文を写す。 貴墨、殊更御国名物宮重大根弍本被懸芳慮忝(ほうりょにかけられかたじけなく)、尤賞翫可仕候。毎々御懇情不淺(あさからず)、忝奉存(ぞんじたてまつり)候。愈御堅固珍重、此方露命いまだ無恙(つつがなく)候。当夏秋之比(ころ)上り可申(まうすべき)覚悟に御坐候へ共、何角(なにかと)心中障る事共出来延引、浮生餘り自由さに 心變猶々難定(さだめがたく)候。 一、短尺(たんざく)十三枚、其後戸田左門殿表より之便りに七左衞門殿迄頼、又々進じ候。 猶追々力次第に頼候而上せ可申(まうすべく)候間、老養御樂み可被成(なさるべく)候。此比は發句も不仕(つかまつらず)、人のも不承(うけたまはらず)候。猶思ひ付候而(て)重而之便りに可懸御目(おめにかくべく)候。七左衞門殿へも御無さた、心計(ばかり)は何としてかとしてとのみ存候而、御書状さへ不得御意(えず)候。御懐敷(なつかしく)候。其元連衆如風様へも可然奉頼(しかるべくたのみたてまつり)候。御使も(ま)たせ置、返事したゝめ候故、何を書候も不覚(おぼえず)候。無常迅速々々。 極月一日 蕉桃青 判書 寂照様 貴報 尚々俳諧等折々御坐候哉、承度(うけたまはりたく)候。誠々(まことにまことに)遠路不絶(たえず)御案内のみならず、御音信、御心ざし厚き事筆頭難盡(ひつとうにつくしがたく)候。 冒頭にいう「御国名物宮重大根」は別名尾張大根。現在の愛知県西春日井郡春日村宮重の原産で、根の約三分の一が地表に出て緑色になるというから、アオクビ大根に似たものか。甘味に富み、煮るか切干にして食すが、芭蕉に届けられたのはどうも沢庵であったようだ。宮重種は沢庵にするには最上とされる。芭蕉は門弟たちからこうしたこまごまとしたものを、折あるごとに送られていたようだ。同じ年の寂照宛書簡(閏三月十六日付)では「髪剃壱丁、對一本(何の対かは不明)」の礼を述べているし、さかのぼって天和二年三月には木因から干白魚一箱を送られている(もっとも干白魚などは当時の生活水準を思えば必ずしも「こまごまとした」ものではなかったかもしれないが)。 ところで次の「当夏秋之比上り可申覚悟に御坐候へ共、何角心中障る事共出来延引、浮生餘り自由さに心変猶々難定候」というくだりだが、この時期、上洛のこころざしを洩らしたのは「当秋冬晩夏之内上京、さが野の御草庵に而親話盡し可申とたのもしく存罷有候」という、貞享三年閏三月十日付の去来宛書簡あたりが初見である。それが六日後の寂照宛では「何角障事共心にまかせず候而、いまだ在庵罷有候。夏之中には登り可申候間」というニュアンスになっており、十月末の同じく寂照宛で「拙者も当年上京可致候へ共、もはや寒気移候故思ひ留り候」と、はっきりと上洛を断念している。このような経緯をたどった上洛のことであるからには、一見読みすごされてしまいそうな「…上り可申覚悟に御坐候へ共」といういいかたは正確ではない。すなわち『書簡』註にいう「…候ひしか共」が正しいかたちである。また「浮生餘り自由さに」云々でいう「自由」は勝手気ままという意味であり、ここらあたりに相手への謙遜とも、芭蕉自身のこころのポートレートともつかぬ複雑な色合いが見え隠れするようだ。私には、この時期けっこう俗事に追われていた彼の姿を想像することができる。 現に貞享三年閏三月の寂照宛では、上京修行に出るかねて知りおきの僧二人の世話を依頼したり、他門のものも含めた少なからぬ数の短冊揮毫を頼まれたりしている。とりわけ短冊揮毫の一件は、当書簡でも「短尺十三枚、其後戸田左門殿表より之便りに七左衛門殿迄頼、又々進じ候」と触れられており、書簡に見るかぎり貞享三年三月から四年正月に至る十か月に及んでいることを考えてみても、この時期の寂照宛書簡の主な目的のひとつがそこにあったということができるのである。なお「戸田左門殿表」とは大垣藩主戸田侯の江戸藩邸のことで、芭蕉はそこを尾張・美濃への連絡口のひとつとしていたことが知られる。おそらく最初期の美濃蕉門である中川濁子や谷木因の縁によるものであろう。連絡口はほかにも江戸麹町の寂照千代倉屋の江戸支店などがあったと推定される。また「戸田左門」については、『書簡』註に「大垣藩主戸田左門氏西(うじあざ)を指すが、貞享二年に采女正氏定の代になったばかりのため誤ったもの」とある。「七左衛門」は林桐葉の通称。熱田の蕉門で、芭蕉を寂照に紹介したのはこの人ではなかったかと考えられる。 さて、この書簡のなかで最も注目されるのはその次の一節「猶追々力次第に頼候而上せ可申候間、老養御樂可被成候」といえよう。寂照当時四十七、芭蕉この年四十三、俳諧を老後の楽しみとして相手に勧めている文面だが、当然芭蕉自身にも「老い」の自覚はあったものとみられる。現在から考えると早すぎる自覚のようであるが、元禄六年の許六宛書簡で「老の名の有共しらで四十から」という一句を報告しているように、当時としては常識に類するものであった。しかしそれにしても「老養御樂」とは陰影のある言葉だ。後年の遺状のなかでも「弥(いよいよ)俳諧御勉(つとめ)候而、老後の御樂に可被成候」、「…老後はやく御楽可被成候」というように繰り返し述べられており、私にはこれが芭蕉という存在が含む謎のひとつであるような気がする。これについては解がないわけではない。支考はその著『俳諧十論』で「今はた此意を論ずるに、若き時は友達おほくよろづにあそびやすからんに、老て世の人にまじはるべきは此たヾ俳諧のみなれば、是を虚実の媒にして世情の人和とはいへり」と説くが、一面にすぎないように思う。私には「老後の楽しみ」を「死後の楽しみ」と読み替えてみたい誘惑をうまく抑えることができない。書簡の最後、「御使も(ま)たせ置、返事したゝめ候故、何を書候も不覚候。無常迅速々々」というくだりなど、老耄というよりはむしろ打てばひびくように用意されてある俳諧師の内面を思わせるものであるが、そう観じている芭蕉の眼に人生はひとつの夢幻と映ってはいなかったか。彼にとって「老い」とはそんな夢幻のかたちをとって(同時代人の常識をやや逸脱して)おとずれていたように思う。それは必ずしも遺状にいう「杉風へ申候。久々厚志、死後迄難忘存候」という執着を思わせる文言と矛盾していない。ここで芭蕉は自らの死をそれまでの俳席のようにさりげなく「転じて」みせている。遺状で繰り返される「死後迄」という言葉は彼にとって最後の鬼気迫る滑稽であったと私はみる。そこから老いのその「後」にあるはずの、人にとっては見果てぬ夢幻まではそう遠くないのである。 (この項終わり)
|
| 批評的切片 肌の幻影 2 |
清水鱗造 |
一 近代詩によって成された方法 1 (承前) 朔太郎の詩における微細なものの暗喩は自己意識(神経)の微細な動きを拡大して示すことを実現している。これが何を意味するかといえば、その方向に無限に喩の通り道のための穴を開けたということである。微細な感覚的な体験、とるに足らないようにみえていた視覚的体験や夢が、そのまま自己意識の自由な振舞いを表わすことを拡大できるということ。生活的感性の延長線上にあたかも病者の領域が実は普通に存在することはだれでも知っていたことだ。そういった領域の表現の拡大が近代から繰り広げられることによって、逆に生活者からいえば新たなコミュニケーションの領域が拡大したのである。だが、詩がそういう見方からは全然別なところで集中されて行なわれているということは科学と同じである。 光る地面に竹が生え、 青竹が生え、 地下には竹の根が生え、 根がしだいにほそらみ、 根の先より繊毛が生え、 かすかにけぶる繊毛が生え、 かすかにふるへ。 かたき地面に竹が生え、 地上にするどく竹が生え、 まつしぐらに竹が生え、 凍れる節節りんりんと、 青空のもとに竹が生え、 竹、竹、竹が生え。 みよすべての罪はしるされたり、 されどすべては我にあらざりき、 まことにわれに現はれしは、 かげなき青き炎の幻影のみ、 雪の上に消えさる哀傷の幽霊のみ、 ああかかる日のせつなる懺悔をも 何かせむ、 すべては青きほのほの幻影のみ。 (〈竹〉全行) 口語自由詩を標榜するかぎり、どんなに生活破綻者に見えても試行は続けられるというように、文学的要請は一般的な〝生産〟と〝欲望〟の埒外にある。そこに関係の糸を見つけるとしたら、偶然に投射されるなにものかだ。そのものを一般的な〝生産〟〝欲望〟の側からみたら、危機感を持たれることになる。逆に彼らにそのまま認められたらそれだけで、おしまいだという意識も詩をつくる側は持つかもしれない。 イリュージョンとしての〝竹〟は、時代の叙情と信じられてあるものに微細な観察の表現を追加する。《根の先より繊毛が生え、/かすかにけぶる繊毛が生え、/かすかにふるへ。》というところまで、自らの神経の暗喩を届かせることによって、エディプスの三角形からかたちだけでも遁走できるという実用的な(?)機序もある。 一九二九(昭和四)年七月下旬、朔太郎がふたりの娘を連れて前橋行きの汽車に乗り込んだとき、それがごく自然にみえることによって、重層したものの単純化を試みることもできる。 詩の表現の目的は単に情調のための情調を表現することではない。幻覚のための幻覚を描くことでもない。同時にまたある種の思想を宣伝演繹することのためでもない。詩の本来の目的は寧ろそれらの者を通じて、人心の内部に顫動する所の感情そのものの本質を凝視し、かつ感情をさかんに流露されることである。 詩とは感情の神経を掴んだものである。生きて働く心理学である。 すべてのよい抒情詩には、理屈や言葉で説明することの出来ない一種の美感が伴ふ。これを詩のにほひといふ。(人によつては気韻とか気稟とかいふ)にほひは詩の主眼とする陶酔的気分の要素である。 (『月に吠える』一九一七(大正六)年、〈序〉より) 近代の抒情詩、概ね皆感覚に偏重し、イマヂズムに走り、或は理智の意匠的構成に耽って、詩的情熱の単一な原質的表現を忘れて居る。却つてこの種の詩は、今日の批判で素朴的なものに考えられ、詩の原始形態の部に範疇づけられて居る。しかしながら思ふに、多彩の極致は単色であり、複雑の極致は素朴であり、そしてあらゆる進化した技巧の極致は、無技巧の自然的単一に帰するのである。 (『氷島』一九三四(昭和九)年、〈自序〉より) 後者の引用部分に続いて、思想的には〝日本回帰〟というべきパーレンで囲んだ《この意味に於て、著者は日本の和歌や俳句を、近代詩のイデアする未来的形態だと考えて居る。》というのがあるのだが、この二つの〈序〉の径庭は、自然に娘ふたりと汽車に乗る、という自己劇化の終わりに、《詩の本来の目的は寧ろそれらの者を通じて、人心の内部に顫動する所の感情そのものの本質を凝視し、かつ感情をさかんに流露されることである。》という近代的な詩論が漂白していく、ということに重ね合わせにすることができるようにも思う。この朔太郎的な〝日本回帰〟という課題は歴史的パラテキストによって、さらに解釈を進めることができるし、それをした評者もいるのだが、別項に譲る。 まず問題なのはさまざまに挫折また変節した、五感を追究する方法がどこまでいっているかということだ。〝陶酔的気分〟ということは、朔太郎や白秋や犀星らの概ねの資質に還元することができる言葉であるが、彼らが同時期に書いた詩のにおいは共同でこれをつくっていたという詩史的な見方もできる。その分〝にほひ〟は稀薄になったともいえるのである。 山村暮鳥に比べれば、朔太郎の詩は罪障感や鬱を表わすことによって、より立ち上がってくる。山村暮鳥らの詩を読んでいると、テレビのなかった時代のことを想像させられる。一方で愉楽のほうへ傾き、一方でもっと重層した深みのほうへいく、といった単純な言い方もできるかもしれない。だが、環界を受け取る五感の瞬間だけを言葉にすることを徹底してやることが、線形なものだけでなく非線形なものも表わしうるのではないか、という課題が次にくる。その意味では山村暮鳥の詩は、ヒントを与える詩人である。 洋傘(パラソル)の女が二人、 その影と、柔かい光りの中を動いて行く。 此の時、空の群集より、 花弁のやうな蝶、 菜の花圃(はなばた)へ眠りにゆく時、 昼の神経が光り、 次第に光る、 ちやうど玻璃の窓のやうに。 丘より匂ふ白色と、暗い心に…… 夢に…… 眼瞼に…… (――蝶と女と窓との音楽。) 神経の匂ひつかれた昼の外部、 路側の花のかゞやき。 (〈蝶と昼の神経〉全行) ちょうどこの詩には〝にほひ〟と〝神経〟という、『月に吠える』〈序〉にでてくる言葉もでてくる。このにおいに朔太郎は鬱などのナーバスをしみこませたといってもいい。宮沢賢治の自称〝心象スケッチ〟が、広義の意味の詩ではないと自身で感じられていたことには、それが試行であることと線形的な詩史からの逸脱を感受していたからだ(賢治の心性からいって自恃という言葉は似合わない)。が、暮鳥がヒントになったことは疑えないことではある。 『月に吠える』の〈序〉の〝にほひ〟をそのまま尊重して、分離した概念にしてしまったらどうであろうか。当然ながら、それと重ねあわせるように統一的なものの分離が起こる。それもまた〝ある種の思想〟に収束するのである。ここに退廃への水路ができることもまた否定できない。もうひとつ別に、一人の詩人のなかにあっても、オリジンとそのオリジンから下に流れている詩が存在する。しか詩史的なオリジンと、資質的なオリジンとはまた別ではある。この時代の唯美派と呼ばれるような一群の詩人は、こういう見方でその作品の細部を日のもとに晒すこともできる。しかし、還元不可能なものが、ほとんど沈黙に近い個的な喩であるとき、謎であるのか罠であるのかということは、微分不可能な言葉の本質に関わる。 (この項つづく)
|
| 〈都市を巡る冒険〉 新宿・渋谷・池袋(四) 小鳥語 |
清水鱗造 |
カウンターの向こう側のマスターが、ちびりちびり飲んでいる僕に話しかけてきた。 「そろそろ来るかな」 「そろそろ来るって?」 その店は新宿の路地裏でも目立たないところにある。古い石畳の舗道を鉢植えの植物や、自転車などを見ながら、店に着くとたいてい客は僕ひとりだ。時間が早いせいもあるかもしれない。 「水曜日はね、Nさんが来るんだよ。たぶん興味もつと思うよ」 「なぜ?」「来ればわかるよ」 最近、飛行船をみることがいやに多い。この日も夕刻ぼんやりと街の明かりに照らされた飛行船をみた。それは新宿御苑上空あたりでゆっくり旋回し、のんびりした牛のようにお尻を向けて去っていった。一杯めの水割りを飲みながら、そのイメージを咀嚼していた。かすかに酔いがまわってくる。 突然、ドアが開いた。そこにはスーツにネクタイを締めた初老の男が立っていた。 「ピピキュ!」 一瞬、混乱した。椅子に座ると、その男はマスターに向かって、こう言った。 「ピーピュルルリ、リリリルーピロ」 マスターは何もいわずに、ビールを男の目の前にだした。そして、こちらを見てほほえんだ。 「まず、ビールをください、って言っているんですよ」 その男は小鳥語を話すという。マスターはわからないが、だいたい要求するものはわかる。それで対応しているのだという。店に来はじめたころは、日本語を話した。それで彼がどこかの大学の教師だということはわかっている。その男は急にこちらを向いた。 「ピーピュリンリンリン、リルレロラレロン」 なんだか、僕には彼が「この店、初めて?」というように聞いているように思えた。 「三回めぐらいかな」 僕が答えると、かれはにっこりして静かに飲み始めた。そういえば、電車のなかでどうしても何語か推測できない言葉で呟いている女性をみたことがある。その若い女性は正面にきた中年の男性にしきりに話しかけた。その女性が清楚だったからだと思うが、彼はいぶかしげななかにも親切に聞き取ろうとしていたように見えた。しかしあまりしつこいので、次の駅で降りてしまった。そのことを思いだした。 音楽は、レゲエを流していた。また、小鳥おじさんは言った。 「プリーキュラン、スープレットラリラリラリ、モーツァルト、リンリンリンリーピンリン」 「モーツァルトの弦楽の『不協和音』という曲をかけてくれ、って言ってんですよ」 この時点で酔いの回った僕は開き直った。 「ガーギグガガガガ、ゲゴギンゴガンガゲゴギーン、グゴグゴゴギグゲゲゲゴーン」 |