詩 都市 批評 電脳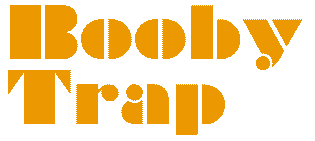 第11号 1993.12.25 206円 (本体200円)〒154 東京都世田谷区弦巻4-6-18 (TEL:03-3428-4134:FAX 03-5450-1846)(郵便振替:00160-8-668151 ブービー・トラップ編集室) 5号分予約1000円 (切手の場合72円×14枚) 編集・発行 清水鱗造 *郵送料が1月より値上げされるため、次号より\227(本体\220)となります。5号分予約\1100(切手の場合90円以下の小額切手)となりますのでご注意ください。1月15日までに予約の方は旧料金でOKです。 |